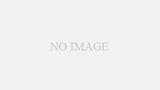2019年11月05日公開
2020年04月02日更新
日本一の秘境駅「小幌駅」とは?鉄道マニア必見の陸の孤島!廃止寸前?
JR室蘭本線小幌駅は鉄道マニア系人気ユーチューバーも訪れる日本一の秘境駅です。その理由は周りは民家はおろか道さえもない完全に下界から隔絶された秘境の駅だからです。特急「北斗」が鼻の先で全速力で駆け抜ける、トンネルに幽霊が出ると噂の恐怖体験スポットの小幌駅です。

小幌駅とは
小幌駅
JR北海道の室蘭本線の駅。日本一の秘境駅として知られている。駅の東側と西側はトンネル、北側は山で道はない。南側は唯一道があるが獣道でその先も海岸で何もない。降りることは出来ても乗ることが出来ない駅である。 pic.twitter.com/FPImadjUGR— 鉄道旅図鑑 (@tetudou_bot) October 28, 2019
小幌駅とはJR室蘭本線にある無人駅です。周りが険しい山に囲まれて一方は海岸につながっていて市街地へ抜ける道がなく、小幌駅から脱出する手段は唯一鉄道だけという秘境駅です。また特急はおろか一部の普通列車も通過する駅で、下り東室蘭行き1日2本、上り長万部行き1日4本しか本数がないまさに秘境といえる駅です。
全国には秘境駅がたくさんありますが、その中で小幌駅は秘境駅ランキングで1位を独走していて、まさに全国の秘境駅のキングオブキングと謂える駅です。
JR室蘭本線の秘境駅
そんな人も寄せ付けない三方が断崖、一方が海に囲まれ、抜ける線路は駅の両側がすぐトンネルとまるで要塞のような秘境駅である小幌駅ですが、なぜこんなところに駅があるの?と思われた方もいると思います。元々は室蘭本線が単線だった時代に機関車の行き違いの信号所として設置されました。
設置されたのは蒸気機関車がまだ全盛だった1943年(昭和18年)。まだ鉄道の登坂技術が未熟だった時代、トンネル内を急勾配を登っていく蒸気機関車に対して、トンネル外で少しでも勾配が緩やかな場所に信号所を設置する必要がありました。
1位小幌駅( ̄~ ̄;) pic.twitter.com/g2yThJwKrN
— ぴゅあ@乃木坂どこへ (@qXbyAidGvHwrh8Q) October 28, 2019
そこでちょうどこの要塞のような立地がちょうどよかったのでこの地に信号所を設けたのです。この信号所を設けた1943年(昭和18年)に列車の行き違い退避と同時に、仮乗降所を設けて旅客の扱いも同時に開始したようです。
時は流れ戦後になって1967年(昭和42年)この区間を複線化。行き違い退避としての信号所の役目は終わりましたが、仮乗降所としての旅客扱いは継続。次第に無人化されて1987年(昭和62年)国鉄分割民営化に伴いJR北海道に継承された時に駅に昇格して今に至ってます。
秘境駅マニアの聖地
小幌駅の断崖絶壁、人を寄せ付けない、行き方がJRの一部の普通列車のみというこの駅の秘境ぶりは、全国の鉄道マニアに知れ渡っています。というか、鉄道マニアにとっては小幌駅を知っているかいないかは常識の範囲内です。秘境マニアだけなく、多くの鉄道ファン、マニアが小幌駅を訪れています。
YOUTUBEでも小幌駅について多くの動画が上がっていますが、チャンネル登録者二けた万人クラスの鉄道系ユーチューバーたちがここの体験動画を上げています。他にも動画の容量の関係でご紹介できませんが、小幌駅の知名度は鉄道マニアには常識レベルの秘境駅です。
小幌駅の特徴
こぼろー
小幌駅 pic.twitter.com/MHCCeEO2gh— usual ordinary (@OrdinaryUsual) October 23, 2019
小幌駅は日本一の秘境駅で行き方はJRのみ、周りの山に阻まれて抜けるのは海しかないまさに陸の孤島と呼べる秘境ぶりですが、ここではそんな小幌駅について詳しく見ていきます。
特徴①トンネルとトンネルの間にある駅
小幌駅はJR室蘭本線の礼文華トンネルと新辺加牛トンネル(上りは幌内トンネル)の間に挟まれた場所にあります。ホームは2つのトンネルの隣に位置しているので、列車がトンネルを入った時に鳴る警告音が黄泉の国からおいでおいでと呼んでいるようです。
しかもホームの幅は2人並ぶ幅しかなく、特急、貨物列車などの通過列車がトップスピードでいきなり出てくる怖さ。昼訪れた方がこれだけ怖いと言っているのに、北海道の冬の夜の小幌駅に降り立つとどうなるか・・。列車の本数はほとんどないですし、肝試しに訪れたいなら責任は持てませんがはっきりいって怖いですよ。
特徴②小さなホームには保線小屋とトイレ
【駅設備ごあんない】当駅にはお手洗いございます。右がバイオお手洗い、左はどこでもドア。 pic.twitter.com/RPPTu64DrA
— ( ; ;)ゞ小幌駅改札案内(Temp) (@KoboroSta_bot) October 29, 2019
小幌駅には小さなトイレと保線小屋があります。トイレは昔は写真の右側が扉のない汲み取り式だったので女性は真っ青だったのですが、2016年に豊浦町に駅の管理を移管されてから変わったようです。トイレはバイオトイレに変わり、扉もついて利用しやすくなっています。
この小幌駅にはJR室蘭本線の保線資材を保管する保線倉庫があります。この保線小屋の裏手に浜へ出る縄はしごがあります。それ以外駅のまわりは建物らしきものは何もなく山ばかりです。
特徴③外界への道は沢伝いの登山道
昨日は即位の礼正殿の儀でお休み。
室蘭の友人のところへ。この急な坂をくだったところにある小幌駅へ。
こんな道を行くしかないとなると、秘境の駅とか言われちゃいますね。 pic.twitter.com/M4azYKNVRM— usual ordinary (@OrdinaryUsual) October 23, 2019
小幌駅からの行き方には相当の覚悟が必要です。JR室蘭本線のある小幌駅と並行に走っている国道が一山超えたところにあるのですが、そこへ行くのにかなりの装備が必要です。トイレと保線小屋の間を抜けると草むらの道になるのですが、左の木橋を渡ると行ける道はあります。が、やめておいた方がいいです。
高低差100m、距離2kmの獣道を延々歩くことになります。道の痕跡すらわからない道になりますので、遭難のおそれもあり、また北海道の山はヒグマが出ます。もう一つ、沢伝いにいくと海岸へ抜けますがその道も獣道です。道という痕跡は僅かで遭難の危険性もあります。小幌駅からの外界の道はそれしかありません。
特徴④定住人口なしの陸の孤島
日本一の秘境駅・小幌駅。
なっ、何だここは?!
トンネルとトンネルの間にある無人駅だが、ホームの周り3面が山と崖に覆われている。
唯一の山道を行くと海が見えたが険しさのあまり遭難しかけたw。
まさに陸の孤島、現代のワンダーランド! pic.twitter.com/J7TwxqitpI— 産経相 (@GATA3104) September 19, 2015
JR室蘭本線小幌駅周辺には人が一人も住んでいません。小幌駅への行き方も断崖絶壁と海の要塞の場所で外の世界と全く隔離された場所です。今は住んでいないJR小幌駅も戦後すぐの時代は人が住んでいたようです。
小幌駅から小幌海岸へ出る獣道がありますが、かつては夏の海水浴客とキャンプ場客で賑わったようです。その経営なのか少しばかりの民家が立っていたようで今ではその痕跡すらありません。小幌駅へ降りる客は小幌海岸への釣り客か鉄道マニアぐらいで今では人が住んでいません。
かつて「仙人」と呼ばれる男性が住みつく
廃駅と報道されたときに
最寄りの礼文駅から向かった。(小幌駅は車ではいけない)
無人駅なのに
人多すぎて
臨時の警備員や駅員がたくさんいた(´・ω・`)で、現地で人気なり
自治体の援助などで
廃駅はなくなった
今もあるみたい(´・ω・`)
昔仙人もいた。 pic.twitter.com/wCxKHZQyVh— およよ(o¥o)→11月17日京都合同 (@oyoyo00) July 30, 2018
今は自然しか何もなくだれも住んでいないJR小幌駅ですが2007年まで「仙人」が住んでました。と言っても「ドラゴンボール」の亀仙人が住んでいたわけでなく、「仙人」と呼ばれる年配の男性が小幌駅あたりに住んでいたようです。一説では線路脇の待合室に住んでいたとか。
いつごろから「仙人」が住み始めたのは分かりませんが、北海道の雪が降る厳冬の北海道に誰一人来ない場所に、暖房もなしに住み続けた「仙人」がなぜそこに住んでいたのかは謎です。
写真のように住んでいたかどうかは分かりませんが、一説では「仙人」は20年も小幌駅近辺にすんでいたとか。周辺は崖で切り立ったところが多く、ロープやはしごがないと転落して死ぬことがある個所ばかりです。そんな獣道みたいな場所に「仙人」がベンチで腰かけて暮らしていたという話もあり、どうやって「仙人」が小幌駅近辺で暮らしていたのかは分かりません。
そんな「仙人」ですが2006年の秋、衰弱した状態で発見、救助ヘリで救助され手当ての甲斐もなく翌年亡くなりました。「仙人」が救助された様子は翌年TVの警察特番で報道され、全国に知られることになりました。10年経った今でも「仙人」は伝説になってます。
特徴⑤駅近くのトンネルは心霊スポット?
小幌駅のトンネルから列車にひかれた霊がトンネルの奥から出てくる。そんな心霊話もあるようです。10年前、近くの海岸で遺体となって見つかった母と幼児が、前の日に小幌駅を降りたという話もあり、本当のところはどうか確証はありません。
ただ冬の雪が積もる中での夜に小幌駅での電車の待ち合わせの時、寒い中で列車がトンネルに入った時の警告音がトンネル内に鳴り響くのはリアル心霊で怖さを感じます。寒い中でホームが雪でカチカチにになり、周りが暗闇でトンネルから音が聞こえる。そっちもリアルに心霊話です。
小幌駅は廃止される?
小幌駅1943年(昭和18年)に開設された小幌信号所として開設されました。同時に客扱いも始めたのですが、当時は数件の民家と海水浴客に利用されていました。その数件の民家が無くなり、海水浴客も見込めなくなった小幌駅をJR北海道は廃止の方針を打ち出しました。ここではその経緯について見ていきます。
2016年に廃止する方針を表明
★秘境・小幌駅★
2015年9月のJR北海道小幌駅。
駅廃止が囁かれる最中、地元議会の方が視察に来られていた日。
「秘境駅」に約50人が降車し、人だらけに(笑) pic.twitter.com/hEOPnMOum1— バイクで廃線旅行? (神奈川県 横浜・海老名) (@rsr_kh400) January 19, 2017
行き方も困難で民家も無く、誰も日常生活では使っていない駅ーJR北海道は国鉄時代から引き継いだ小幌駅に採算性を見込んでいませんでした。国鉄時代に民家や海水浴などの必要性があった小幌駅ですが、経営の観点からすると誰も日常的な利用がない駅に維持費はかけたくない、廃止はやむを得ない。JR北海道はそう考えていたのです。
あとでご紹介しますが、地元豊浦町が小幌駅存続に廃止したがっているJR北海道と話し合った際にJR北海道社長から出た言葉があります。「鉄道マニアの為に小幌駅にコストをかけて維持していくべきか?」しかし豊浦町としてはこの小幌駅をなんとしても残したい理由があったのです。
1年ごとに存続の是非を判断
◆12/20(火) 北海道新聞朝刊 P.24
「日本一の秘境駅 小幌・上 ~廃止一転 町が維持管理~」幌延町「小幌駅を参考にした。今後、視察も検討したい」
小幌駅が先行事例に…。 pic.twitter.com/PeLtdGEguN— 幌延まちおこし隊。糠南ガンバ✊ (@horo_nukanyan) December 19, 2016
豊浦町は小幌駅廃止を何としても阻止しようと動きました。理由は小幌駅周辺の海岸は世界ジオパークに認定されていて小幌洞窟を目玉にした観光コースを提案、国に交付金の申請をしていました。行き方が小幌駅しかないこの区域に駅を廃止することは豊浦町にとって観光の目玉にすることができなくなります。
廃止前提のJR北海道に豊浦町が存続を強く要望した結果、最初は廃止の前提を崩さなかったJR側が態度を軟化し「駅の維持コストを豊浦町が負担してくれるなら存続も考える。」豊浦町は維持費用を当面負担し、1年ごとに廃止・存続の是非を検討することに最終的に合意しました。
小幌駅周辺の見所
#北海道 #駅
室蘭本線 小幌駅
2018.3.17
車でのアクセス不可のため、日本一の秘境駅とも。2015年に廃止が伝えられると惜しむ声が多くなり暫定存続が決まったという珍しい駅。時刻表よく調べて行かないと🔍👓大変なことに…💧。 pic.twitter.com/dXnkFgof41— ゆーから (@Love25227122) July 7, 2019
小幌駅の周辺は世界ジオパークに認定された海岸が見どころです。アスファルト舗装・水洗トイレなどの整備は行き届いてなく、行き方は登山靴などの山登りの装備が必要ですが、裏を返せばそれだけ人だけ手を付けていない手つかずの自然が残っています。
余談ですが、小幌駅周辺をを訪れるときは行き方も危険な個所もあるので装備は万全に準備しましょう。またトイレは小幌駅しかありません。周辺にはトイレは設置していませんので体調は万全に整えるとともに、帰りの行き方もすぐに帰れないので、事前に小幌駅で済ませた方が無難です。
見所①小幌洞窟
天安河原。
でっかい小幌観音みたい。 pic.twitter.com/vLxpUPtKmo— 茶! (@cha_558khz) July 29, 2016
小幌駅から20分、登山靴などの装備が必要な行き方が必要な場所ですが、到着するとプライベートビーチのような空間のビーチに到着します。小幌洞窟はその右手にある洞窟です。洞窟の中には岩屋観音が祀られています。海岸に出ると建物はありますが、そこはトイレではありません。
小幌洞窟ははるか2000年昔の縄文時代、縄文人がこの洞窟に住んでました。この洞窟から7体の縄文時代の人骨が発見され、土器や石器も見つかっています。どうもこの洞窟は定住の場というより一時的なキャンプの場として利用されたようです。
見所②岩屋観音
また、小幌駅から約20分歩くと、岩屋観音がある。かつて円空が仏像を彫ってここに納めたらしい。 pic.twitter.com/mgkDv9XgQr
— YANGE (@shepherd_city) August 23, 2018
岩屋観音は小幌洞窟の中にあります。ここへの行き方も普段着の装備では危険です。また自然の中にあるためトイレなどの近代設備はありません。岩屋観音は江戸時代の美濃国(今の岐阜県)出身の僧、円空が作った観音像をこの洞窟の中で祀ってました。今は岩屋観音は別の所に安置されています。
また円空は小幌洞窟に最初に訪れた本州からの人です。訪れたのは1666年(寛文6年)3年前に近くの有珠山の噴火を知って海を渡ったようです。そして有珠山や洞爺湖、善光寺に参詣して5体の仏像を納めたそうです。その道中というか、ここへ訪れたのもその途中だったと思われます。
岩屋観音は首なし観音
小幌駅から海に出ました。岩屋観音です。 pic.twitter.com/tsPI8bHFtA
— ヴォストク (Vostok Saporovskii) (@vostok061) August 8, 2015
この洞窟に安置されていた観音像にまつわる話があります。昔日本国内をあちこち回っていたお坊さんがこの近くの道を歩いていた時、突然大熊に襲われ、必死で逃げて小幌洞窟にたどり着き、中の仏像の裏に身を隠していると、その大熊はその仏像の頭を食いちぎってどこかへ行ってしまいました。
2回の転倒の末、小幌洞窟と岩屋観音制覇です!海がめちゃくちゃ綺麗なのでここでちょっとゆっくりしてから戻ります #翔音旅程 pic.twitter.com/nUChr8pE76
— 清希翔音🎨@フットバ9駅45 (@kiyoki_kakene) March 25, 2019
このお坊さんはは助かり、そのことを地元の人々に伝えました。以来この仏像は「首なし観音」として今も崇められています。時は流れて人々の信仰の対象になっていた観音像ですがある時、一人の男性に夢で仏像の頭を直してくれるよう仏様から依頼を受けたそうです。
その仏像を函館の仏師に持ち込んだところ仏師も同じ夢を見たそうです。そして観音像の首は付け替えられ今に至っています。
見所③文太郎浜
小幌海岸(文太郎浜)で沈む夕日を見る。
こっちのタグの方が楽だなぁw pic.twitter.com/xOv11uUXJb
— Hiro (@12751Hiro) September 12, 2019
文太郎浜も登山靴など山登りの装備でないと行き方が難しい場所です。ただし岩屋観音よりも距離が近いです。但し獣道になっていますので、マムシなどの危険生物には注意です。また近くにトイレはありませんので事前に済ます方が無難です。
文太郎浜は岩屋観音のある岩屋海岸より広く、天気のいい日には夕方には美しい夕日を観ることができます。またこの近くに「仙人」が住んでいたとされる住居跡があるみたいですよ。
見所④ピリカ浜
昔は民宿があった場所も現在は何もなく。。。ここはピリカ浜と呼ばれているようです。2006年撮影。このころはまだ小幌の仙人ハウスがありました。 pic.twitter.com/Y65sdmW0Cx
— 北の貧乏おじさん (@kitanoossan) July 13, 2014
ピリカ浜は文太郎浜の隣にある海岸です。といっても隣とはいえ間に断崖絶壁があり、浜同士すぐにいけるものではありません。小幌駅からはやはり登山装備で向かうことと、マムシなどの危険生物には注意が必要です。
ピリカ浜へは小幌仙人の住居跡をかすめながら獣道を進んでいくと、天にまっすぐ伸びた立岩がありますので、それが目印になります。あとは危険ですが浜へ降りる崖を降りるとピリカ浜へ到着します。ここの浜を含めた一帯は洞爺湖有珠山ジオパークの一部に組み込まれています。また穏やかな日は夕日も美しいです。
小幌駅で起きたちょっと怖い事件
小幌駅はお化けが出る心霊スポットで決して夜、行ってはならない場所・・ではありません。でも実際にお化けが出なくても雪が積もる寒い夜に小幌駅にいるのはリアルに危険です。待合室はない、ホームの幅は狭い、周りが山と海に囲まれてい一人いない。
こんな場所で寒い時に待ち続けていたら体が冷えます。そんな時に特急列車が鼻先5cmで130kmの最高速度で通過されたらまさにリアル心霊です。そんな状況下のもとで起きたある事件をご紹介します。
普通列車が通過しお客が置き去りに
その事件は厳冬真っ只中の1月21日に起きました。15時45分ごろ小幌駅で乗客2人が列車を待っていましたが、待ち合わせていた普通列車が小幌駅を通過。吹きさらしの待合室も無い小幌駅ホームに取り残される事件がありました。
心霊的にいうといつ雪女が現れてもおかしくない状態。現実的に話を戻すと気温が氷点下まで下がる小幌駅で長時間待たされることになるといつ低体温症になってもおかしくない状況です。気温が氷点下の中で乗客の一人がJRに状況を説明しました。
そろそろ最終だけど、乗り遅れたら、こんなとこに置いてけぼりやからな。キャンプしに来たんなら別やけど(´・ω・`) pic.twitter.com/KEEFxUnm0O
— ( ; ;)ゞ小幌駅改札案内(Temp) (@KoboroSta_bot) November 4, 2019
夏の夜、写真の雰囲気の小幌駅です。夏でも写真のような状況で取り残されるのは怖いです。心霊スポットといわれても仕方ないですが、この状況での冬に起きた事件は健康的にも危険が伴うものでした。
事件の話の続きから、乗客が向かおうとしていた室蘭方面の普通列車は1日3回、次が17時55分で2時間10分待ち。氷点下の中待てるものではありません。JRは連絡を受けて、後続の室蘭方面行の特急北斗を臨時停車させようとしましたが、間に合いませんでした。
特急・北斗が停車
小幌で普通に通過されたから電話したら輸送司令長と話して北斗が止まったんだけど…. pic.twitter.com/WCjISj8Rl6
— ぬ (@tgahjdgjdf) January 21, 2016
事件の話の続きですが、結局反対方面の函館行特急北斗12号が小幌駅に臨時停車し乗客2人を拾って事件解決に至りました。このtwitterは事件の当事者の撮影の映像ですが、ホーム1両しかない小幌駅に特急北斗の先頭車両に乗せようと段取りしているところです。
なぜ本来停車しなければならない普通列車が通過したかは、小幌駅自体がダイヤ的に普通列車でも一部通過する列車があって、運転士が停車か通過か確認せずにうっかり通過してしまったことが原因です。運転席には秒まで定めたタリフという運行表があり、停車かどうかはそれを確認すれば起こらなかった事件でした。
ウイイイイイイイッッッッス。どうも、つけ麺で〜す。
まぁ今日は、小幌駅で汽車に乗ったんですけども、乗客は、誰1人、いませんでした…。 pic.twitter.com/jVfO7WB1ZJ— 🍒 つけ麺 🍒 (@ya_do_mo_do_mo) November 5, 2019
厳しい言い方をするとその確認を運転士が怠ったのですが、もし乗客がそのまま2時間余り待つとなると、高速運転で通過する列車、暗闇でトンネルから聞こえるピー、ピーという警告音、小幌駅近くの海岸で心中事件が起こった話、思い出すとその状況で余計震えるのではないでしょうか?
間違っても心霊スポットとして肝試しで冬の夜に降り立つのはやめた方がいいです。リアルに本数が極端に少なく最悪、自分自身が事件の当事者になりますから、心霊体験で冬の夜の小幌駅に降りるのは非常に危険です。冬の夜に降り立つのは、集札の際、運転士も心配で聞くぐらいですから。
小幌駅への行き方
今!小幌駅に居ます!
昨日も来たけどねえ! pic.twitter.com/PCweaYlVtG— 貨物列車激走チャンネル (@Chachagirls8) November 4, 2019
日本一の秘境駅、あるいは怖さを体験するリアル心霊スポットの小幌駅ですが、要塞のような地形に立地しているので列車しか簡単にアクセスできる方法がありません。しかも普通列車が一部通過する駅で、忘れ去られたようで廃止も取りざされたこともあるほどです。
ここでは小幌駅へのアクセスと、難コースになりますが、車での小幌駅へのアクセスをご紹介します。
JR電車で行く
室蘭本線【キハ40 354】JR北海道🚇
長閑な正午過ぎ発車~まったり空いてて旅気分🚇 pic.twitter.com/whZfq0WZk5— 英語で室蘭をガイドしよう! (@muroran8989) November 5, 2019
大ざっぱにいうと小幌駅はJR室蘭本線洞爺~長万部の間にあります。どちらかというと長万部から洞爺方面へ2駅目が小幌駅になります。当たり前のこと書くかもしれませんが、”日本一の秘境駅”といわれる小幌駅ですので大都市の2駅とは感覚が違います。
まず小幌駅への最初のアプローチは特急北斗が停まる長万部あるいは洞爺下車になりますが、利用しやすいのは長万部下車です。時刻表は後で表にしますが、洞爺からのアプローチは帰りもそのまま長万部行きに乗った方が本数が多いので便利です。
小幌駅の時刻表
今や日本一有名な秘境駅と化した小幌駅。いざ到着してみれば降車・乗車ともそれぞれ5〜6人いて、加えて工事関係者が団体状態で大勢待っており全く秘境感がありませんw なお小幌駅の上下線時刻表はご覧のとおりです😅 これで全部なので御座います(;´∀`)#秘境駅 #JR北海道 pic.twitter.com/jpMbaOh7Sz
— まいたけ????🇨🇳標高0から4000m 地を這ってゆけ天空への道 (@mytake1986) August 7, 2018
小幌駅は一部普通列車が通過する駅で駅のの発着本数は下り(洞爺方面)2本、上り(長万部方面)4本の合計6本です。小幌駅へは時刻表を片手に十分な計画の元、訪れるのがおすすめです。(2019年10月現在時刻表。常に最新のものを確認願います。)
| 長万部→ | 小幌→ | 洞爺 | 洞爺→ | 小幌→ | 長万部 |
| 15:26 | 15:35 | 16:09 | 8:12 | 8:38 | 8:55 |
| 19:28 | 19:38 | 20:11 | 14:46 | 15:13 | 15:32 |
| 17:06 | 17:39 | 17:56 | |||
| 19:38 | 20:04 | 20:21 |
おすすめのコース
そしてまた小幌駅へ
長万部〜東室蘭を結局3回。はまなすで、普通で、帰路は普通とスーパー北斗で行ったり来たり。これが不均衡時刻表の対応。 pic.twitter.com/NAION4vtlY
— モンモンʕ•̫͡•ʔ (@monmon_katsu) September 13, 2015
小幌駅へは登山装備などの十分な装備をされて小幌駅周辺のスポットを訪れたい方は、朝一番の東室蘭発7時22分の普通列車利用しかありません。その後15時台まで列車がありませんが、岩屋観音、小幌洞窟など山登りが必要な行き方の場所に行くときに便利な列車です。
小幌駅のみ見てほんのちょっと体験して帰りたい方は、30分ほどですがおすすめのコースがあります。東室蘭13時55分発の普通列車利用で、途中洞爺14時46分、小幌着15時13分で下車し、帰りは小幌15時44分洞爺16時9分、東室蘭16時55分着の列車で引き返すルートです。
小幌停車ッ~夜バージョンはコチラッ~ですな~一人だけ下車しましたな~#室蘭本線#青春18きっぷ #豊浦町 #小幌駅 pic.twitter.com/lYGsCAKOES
— 北のテッチャン (@kenbou042) September 8, 2019
あるいはおすすめではないので責任は持てませんが、夜の小幌駅の心霊体験コースも組むことができます。すべて最終列車で長万部19時28分の普通列車利用で小幌19時46分、帰りは小幌20時4分で長万部20時21分着のコースです。たった20分の滞在ですが、真っ暗闇の人ひとりいない小幌駅で残された怖さなど、肝試しにはいいかもしれません。
ただし、雪が積もる厳冬にこれをやらないでください。体験している人もいますが本当に凍えますので肝試しどころではないです。そして足元が滑って凍りやすいです。ましてやこのコースは行き帰りとも全てが終電のコース。普通列車通過事件のような事件が起こると一晩小幌駅で過ごすことになりますから・・・。
車で行くには?
小幌駅に徒歩で行くには、37号線のトンネル出口辺りに車を止めるしかない。これが日本一の秘境駅と呼ばれる理由だ。 pic.twitter.com/vcziehOhqa
— 柳原夕士@四日市市 (@plS1dfscLxtRtZl) April 28, 2019
車で直接小幌駅へアクセスする方法はありません。小幌駅近くに国道37号線のトンネル出口あたりに車を止めて獣道を進む方法がありますが、途中で険しい崖やロープ場があり、健脚向けで登山装備万全でないと行くことはできない道です。マムシのでの危険生物にも注意が必要です。
車でのアクセスはここから2駅先の大岸駅で車を止めて小幌駅へ向かう方法です。これなら例えば大岸14時59分発に乗って小幌15時13分、帰りは小幌15時44分発で大岸15時55分で大目に見て1時半半の駐車時間で済みます。
小幌駅の基本情報
北海道にある「小幌(こぼろ)駅」は「日本一の秘境駅」と呼ばれております。#小幌駅#日本一の秘境駅 pic.twitter.com/s6530OhUBm
— 北海道LOVERS (@hokkaidolovers_) November 1, 2019
| 名称 | 小幌駅 |
| 住所 | 北海道虻田郡豊浦町字礼文華 |
| アクセス | JA室蘭本線小幌駅下車 *普通列車のみ(一部列車通過)停車駅 *本数は日に6本しかないので時刻表確認のこと |
| 備考 | 車でのアクセスは不可能。 |
小幌駅は秘境好きなら一度は訪れたい駅
小幌駅→pic.twitter.com/syfDOKn8Sg
— 行ってみたい日本の絶景スポット (@japan_spot_bot) November 3, 2019
小幌駅はかつて海水浴客と数件の民家があった場所でした。「仙人」と呼ばれる男性が2006年に世を去ってから、人が全く住まない駅となり、周りは人を寄せ付けない断崖絶壁と海に囲まれた要害の地、列車日に6本とはまさに行くことが困難な日本一の秘境駅です。
実質の日常の利用者がない小幌駅を、JR北海道は2016年廃止の意向を豊浦町に示しました。豊浦町は小幌駅周辺を観光産業の基盤にしようと考えていた矢先の意向で、何としても存続させたく駅の維持管理費を負担してまで守りました。2019年も1年継続が決まりましたが自然と共に小幌駅が秘境で有り続けるよう小幌駅は今日もそこに在り続けています。
おすすめの関連記事
渡部和幸
人気の記事
-
函館&郊外の花火大会特集!夏の風物詩を満喫!開催日程や時間まとめ!
-
函館八幡宮の御朱印やお守りを紹介!初詣や結婚式に人気のスポット!桜も!
-
【札幌】サッポロビール園を堪能!大人の旅にジンギスカンとビールがおすすめ!
-
【閲覧注意】札幌の驚愕心霊スポット13選まとめ!恐ろしい心霊物件も?
-
函館空港から函館駅までのアクセスまとめ!バス/電車/タクシーの料金は?
-
「札幌市時計台」はがっかり名所ではない!日本最古の時計塔の魅力とは?
-
函館のご当地名物グルメ15選!地元民も御用達の必ず食べたい料理とは?
-
札幌のロマンチックな夜景が見えるレストラン15選!デートや記念日に!
-
函館山に車で行くには?周辺駐車場やアクセスを徹底解説!混雑状況も!
-
子供が喜ぶ!札幌のアスレチックが楽しめる公園13選!大人も一緒に!
-
さっぽろ雪まつりは氷と雪の芸術祭典!有名な雪像は圧巻!日程や場所は?
-
札幌の動物園&水族館3選!子供やカップルにもおすすめスポット!
-
明日風公園は遊具が充実!巨大ジャングルジムや滑り台が人気!夏は水遊びも!
-
札幌初夏の風物詩!YOSAKOIソーラン祭りの見所!2020の開催日程は?
-
札幌のおすすめ日帰り温泉&スーパー銭湯12選!露天風呂や天然温泉まとめ
-
北海道神宮の無料&安い駐車場一覧!料金や場所まとめ!混雑時間は?
-
札幌の室内&子供遊び場27選!雨や冬の寒い日におすすめ!無料スポットも?
-
札幌屈指の桜の名所「円山公園」!周辺の観光&グルメ情報も!まるで秘境?
-
北海道神宮の六花亭「判官さま」は名物限定メニュー!無料で食べられる?
-
モエレ沼公園のアクセス&駐車場情報まとめ!バスはある?駐車場料金は?
新着一覧
-
西のお伊勢さま!「山口大神宮」参拝のご利益や御朱印&お守りをご紹介!
-
米子「とんきん」は地元で圧倒的人気のカレー専門店!人気メニューは?
-
箱根には魅力的なコテージが満載!大人数やカップルにおすすめコテージ16選!
-
岡山の釣りスポットを大特集!人気スポットや穴場スポット16選
-
【岡山発】皮ごと食べられる「もんげーバナナ」はどこで買える?販売店や通販情報を徹底解説
-
【鳥取県】江府町のおすすめスポット15選!人気の観光地や道の駅、ランチやふるさと納税情報も!
-
【聖地巡礼】「千と千尋の神隠し」の舞台やモデルはどこ?油屋&湯屋に似ている旅館10選を紹介
-
岡山のおすすめ鉄板焼きTOP22!高級店が勢揃い!
-
岡山のおすすめキャンプ場20選!デイキャンプやオートキャンプを厳選!
-
岡山のおすすめ温泉20選!露天風呂や日帰り温泉を厳選!
-
漆黒の城「岡山城」の楽しみ方!見どころや御城印がもらえる場所、周辺の観光スポットを徹底解説
-
倉敷の人気うどん屋TOP22!安くておいしい名店が勢揃い!
-
【岡山】美味しい水はここにあり!「塩釜の冷泉」で喉と心を潤そう!周辺のおすすめスポットも解説!
-
千と千尋は四万温泉がモデル!赤い橋や温泉が楽しめる!
-
海のミルク『寄島の牡蠣』を堪能する旅へ!直売所や通販情報も徹底解説!
-
岡山から鳥取の行き方徹底解説!格安で行ける交通手段は?
-
鬼怒川温泉の廃墟群がヤバい!廃墟になった理由とは?心霊現象が起きる廃墟も!
-
暑い夏には岡山へ!おすすめかき氷店20選!桃やピンスの名物も!
-
【市町村別】岡山のおすすめドライブスポット55選!家族・友達・デート・ひとりでも楽しめる楽しい&絶景スポットを紹介
-
【日本三大産地】岡山の牡蠣は大粒でクリーミー!食べ放題や海鮮BBQ、カキオコの人気店全13選&産地直送の人気通販5選!