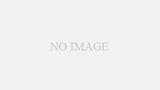2019年12月12日公開
2020年07月06日更新
「赤神神社 五社堂」は999段の石段の上に!なまはげ発祥の鬼伝説とは?
ゴジラ岩のある秋田県男鹿半島には、秋田の風物詩でもあるなまはげとゆかりの深い「赤神神社 五社堂」があります。山道に敷かれた石段を登る先にある「赤神神社 五社堂」に伝わる鬼伝説には、日本の昔話だけではなく、はるか海を渡った中国で名の知れた人物も登場します!

国の重要文化財「赤神神社 五社堂」
赤神神社 五社堂 pic.twitter.com/hiWwe6LK
— 始発です (@super16dx) October 17, 2012
日本海が見渡せる男鹿半島の海沿いには、鬼の形相ななまはげ立像があり、その背後に広がる山中に国の重要文化財でもある赤神神社 五社堂があります。秋田の伝統行事のなまはげと切ってもきれない関係にある赤神神社 五社堂の伝説に迫ります!
秋田の昔話 なまはげ伝説で有名
現在でも伝統行事として男鹿地域で行われているなまはげは、12月31日大晦日の夜(旧1月15日)に鬼の面をつけ藁簑を身に纏い、「泣ぐ子はいねが」「なまげ嫁はいねが」と家々を練り歩く様子で知られています。
秋田県男鹿市 赤神神社五社堂 に参詣 ①鬼が一夜にして積み上げたという伝説がある999段の石段を登って行くと五社堂が見えてきます。各堂の名称は左から十禅寺堂 八王子堂 赤神権現堂 客人権現堂 三の宮堂と称されています。 pic.twitter.com/G4P1hiH5ec
— あきちゃん@ゆっくり 前向きにஐ*⋆ (@akichan0923) August 26, 2016
このなまはげの発祥となるのが赤神神社 五社堂に伝わる伝説です。その有名な伝説によれば、漢の武帝が5匹の鬼を家来として連れ男鹿へやってきたそうです。
そして年に1日だけ正月時期に鬼たちに休日を与えた時の出来事が伝説として現代に至るまで伝えられています。どんな伝説でしょうか?興味がそそられるこのなまはげ伝説に迫ってみましょう!
漢の武帝の鬼の「999段の石段」
赤神神社は999段らしいですけれど、途中から階段じゃないよ。 pic.twitter.com/qFG57LFKsD
— TUNANE (@tunaneru) October 18, 2016
その伝説では、年に1日だけ与えられる正月の休日に喜んだ5匹の鬼たちは人里へ下りて行きます。そして鬼たちは、作物や家畜を奪って大暴れし、里の娘までさらっていくようになったそうです。
困った村人たちは、千段の石段を一晩で築くことを条件に、1年に1人の娘を差し出す約束をします。ただしそれができなければ二度と里には降りて来ないようにと鬼たちに約束をさせました。
そして鬼たちはあと一段というところまで石段を積み上げましたが、村人たちの声真似なのか夜明けの一番鶏の鳴き声に諦め、怒り狂い手近にあった杉を引き抜きながらも約束通り山奥へと帰っていったという伝説です。
「赤神神社」の歴史と伝説
ここまででなまはげの発祥とされる鬼たちと999段の石段にまつわる伝説をご紹介しました。続いて漢の武帝ともゆかりのある赤神神社 五社堂の歴史と伝説へと迫ってみましょう!
赤神神社 五社堂は1216年に建立とされる
今日は五社堂散策 pic.twitter.com/c6EzLNfciY
— 成田義則 (@1954ny) March 24, 2019
現存している赤神神社 五社堂は鎌倉時代にあたる1216年に叡山山麓の山王上七社を勧請したことが始まりとされています。現存している社殿は江戸時代中頃の1710年に建てられたもので、平成の大修理を経て当時の様子を現在に伝えています。
赤神神社の名称の由来は主神として赤神(漢の武帝)を祀ったためとされています。また5つのお堂(五社堂)は武帝が家臣として連れていた5匹の鬼を祀っているとも言われています。
建立から後世になって神仏習合の関連があり、五社堂の各棟を十禅師堂、八王子堂、中堂(赤神権現堂)、客人(まろうど)権現堂、三宮堂と呼称するようになりました。また、赤神(漢の武帝)を祀る場所として奥宮(おくみや)が男鹿三山の山頂にあります。
赤神神社の奥宮は男鹿山頂に!
今日は男鹿市の赤神神社【奥宮】に継ぐ【中宮】、数十年振りの草刈と言うか竹刈 pic.twitter.com/GUzLrPLURz
— 成田義則 (@1954ny) September 15, 2014
奥宮(おくみや)とは山頂と山裾の2つの社殿に同じ祭神を祀る場合に社殿の関係性を指す呼び名で、元々は山頂に本殿があったものが参拝のしやすさから山麓に本殿を移した場合に使用されることが多いようです。奥宮(おくみや)へはたいてい登山をする事が多いです。
重要文化財に指定されている赤神神社 五社堂は、真山・本山・毛無山から成る男鹿三山のうち、海辺に一番近い毛無山の山裾を登り始めた辺りに位置しています。それに比べて奥宮(おくみや)は毛無山を越え、真山の手前の本山山頂にあります。
赤神神社 五社堂から奥宮(おくみや)がある本山山頂まで高低差では500mほどはあることと、山道の状態からはしっかりした登山にあたります。奥宮(おくみや)へ行かれる際は履き慣れた靴で出かけられる事をおすすめします。
赤神神社の伝説「黒神と赤神の戦い」
ナマハゲが積んだといわれる999段の石段を登ると現れる赤神神社五社堂。
朝霧の立ち込める中に5つ並ぶお社は幻想的! pic.twitter.com/5KiSCX13aj— 川北すピ子 (@su_pico) July 15, 2018
赤神神社には黒神と赤神の戦いの伝説があります。黒神は津軽の竜飛におり、赤神は男鹿にいました。そして十和田湖には美しい女神がおり、この女神を中心に黒神と赤神の戦いが繰り広げられます。
最終的には赤神が負け、勝った黒神は十和田湖の女神の元へ向かいますが、入れ違いで女神は同情心から赤神の元へ向かっていました。それを知った黒神は大きなため息を吐き、その吐息で今の北海道は津軽から離れたと言われています。
秋田「赤神神社」の見どころ
ここまでは武帝の降りたったところから始まる赤神神社の由緒に至り、999段の石段にまつわる伝説、なまはげの発祥となる鬼伝説に迫りました。引き続いては現存している赤神神社の見所をご紹介します!
見どころ①鬼が作った999段の石段
今日は赤神神社境内の案内板設置や五社堂石段の修復準備奉仕作業。 pic.twitter.com/o75YRNxmzZ
— 成田義則 (@1954ny) November 24, 2019
武帝が家来として連れていた5匹の鬼たちが一夜にして積みあげたという伝説のある赤神神社 五社堂へと続く石段。伝説では999段ですが、実際のところ何段あるのかは不明です。登り口は海岸線を走る59号線沿いにある赤神神社 五社堂遥拝殿脇にあります。
そして同じ59号線をもう少し先へ行った瑠璃山長楽寺からも登り始める事ができます。赤神神社 五社堂遥拝殿から登り始めると長楽寺までの間に山門もあるようなので、赤神神社 五社堂への道のりをたっぷり満喫されたい方は赤神神社 五社堂遥拝殿から登ることをおすすめします。
赤神神社 五社堂は10~15分の登りです(ガクガク) pic.twitter.com/mvJulLihfq
— はっしー (@hsy_sleep) April 30, 2018
そして登る距離はそれほど長くはなく、慣れた人であれば20分もかからず赤神神社 五社堂までとどりつけるかもしれません。ただ、木々のしげる山道に敷かれている石段を踏みしめながらゆっくりと自然と空気の変化を感じつつ登って行くのも趣きがあっていいですね!
登る際には履きなれた靴で!
階段の様に一定の歩幅で歩ける石段ではなく、斜面に石が敷き詰められているという感じで脚元が不安定な場所も多いため、登山靴やスポーツシューズの様にしっかりと足を固定出来る歩きなれた靴で登ることをおすすめします。
見どころ②石段の先の「五社堂」
いつかの #赤神神社⛩ pic.twitter.com/aRYuCPNKO3
— AnTeNa (@AngusBlue8) October 20, 2019
石段もさることながら、国の重要文化財に指定されている赤神神社 五社堂や赤神権現堂内にある厨子は築年数がとにかく古く、平成の大修理を経て現存しています。五社堂の造りは正面入母屋造様式と呼ばれる平安時代からある様式がとられており、5社それぞれ装飾が違うのでじっくり観察してみるのもいいですね。
5体のなまはげが祀られる
赤神神社 五社堂にはなまはげのルーツとなる武帝の家来5匹の鬼が祀られていると伝えられています。さらに鬼も両親と子どもたちという、男鹿には鬼の子孫がいるかもしれない?と想像が膨らむ言い伝えもあるようです。いずれにしても、昔話や言い伝えによくある教訓が含まれて伝わっているのかもしれませんね。
見どころ③姿身の井戸
赤神神社 五社堂
ナマハゲのモデルになった5体の鬼が祀られている神社⛩
神社までの999段の階段は鬼が一晩で作ったみたい👹
4枚目の井戸は姿見の井戸で水に映らなければ3年以内に死んじゃうらしい。
無事映ったのでセーフ!! pic.twitter.com/6y9NycuBS3— たすくおじさん (@tasuku678) June 6, 2019
石段も赤神神社 五社堂近くへ来ると鳥居があり、その近くに姿見の池があります。この池にはのぞき込んで自分の姿が見えなければ命が長くないという言い伝えがあるそうです。周辺の空気感と合わせて不思議なスポットとされています。
見どころ④御手洗の池
昔の絵には赤神神社 五社堂周辺にたくさんの建物があり、随分と賑わっている様子が伝わります。神仏習合や神仏分離の時代には修験道の修行の場ともなっていたようです。
この御手洗(みたらい)の池にまつわる言い伝えは不明ですが、池の水が張っている時は中島の周囲に輪のようになり、少しの流れもあるそうです。始まりと終わりがなくぐるぐる回る不思議な池と言われています。
「赤神神社」の施設詳細情報
赤神神社 五社堂や石段を実際に見てみたくなりませんか?アクセス情報をご案内しますので、駐車場情報を含めてぜひご参考ください。
「赤神神社」の詳細情報
| 名称 | 赤神神社(五社堂) |
| 住所 | 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川35 |
| アクセス | JR男鹿駅より車で30分 |
| 料金 | 200円(環境整備協力金として) |
| HP | http://www.fun-ms.com/akagami/index.html |
| 御朱印 | あり(無人) |
アクセスの詳細
最寄りの駅はJR男鹿駅となりますが、登り口のある門前駐車場バス停までは12kmはあるため、ハイキング目的でなければ駅からタクシーや車でのアクセスがおすすめです。
また、バスも利用できますが通勤通学時間を除くと平日もほとんど便がなく、土日に至っては運休のようなので、バス移動もあまり現実的なアクセス方法ではないかもしれませんね。幸いにも登り口周辺には駐車場もあるので、おすすめはタクシーやレンタカー、自家用車でのアクセスとなります。
駐車場情報
JR男鹿駅前から59号線を北上するとなまはげ立像がある「門前駐車場」バス停へたどり着きます。このバス停前に駐車場があります。さらに59号線を少し進んだところにある瑠璃山長楽寺周辺にも駐車場があります。どちらの駐車場からも登り口があるので、レンタカーや自家用車でのアクセスがおすすめです。
赤神神社の御朱印はセルフ方式
先日の赤神神社五社堂の御朱印が届いてた pic.twitter.com/fOONLSETsQ
— くさづや (@xauzngawa) August 25, 2018
神社を巡る目的のひとつに御朱印巡りがあります。赤神神社の御朱印はセルフ方式で、五社堂横の無人の小屋にあらかじめ書かれた御朱印が置いてあります。御朱印の日付は自分で記入するようになっています。
お札の購入も可能!
秋田県男鹿市船川港本山門前の赤神神社五社堂にお参りして御朱印(書置き)頂きました。999段の石段を登ります。無人ですが御朱印は拝殿の横の社務所に御守りなどと一緒に置かれています。#御朱印#赤神神社五社堂 pic.twitter.com/hGgrsrHUqO
— HiroB (@HiroBhiro) April 12, 2019
また、御朱印の他にお札やお守り、絵馬も無人の小屋に置いてあるので、やはりセルフですが買い求めることができます。
男鹿の歴史ある「赤神神社」へ出かけよう!
国の重要文化財に指定されている「赤神神社 五社堂」。このように同型式の社が五棟も山中に並んでいるのは全国でも極めて稀とのこと。「鬼が積み上げた」という伝説のある石段、それを登り切った先に厳かに佇んでいました。 #男鹿 pic.twitter.com/oC9Cr0Lygw
— AYANESHIKA (@ayaneshika46) September 6, 2019
年末の伝統行事として秋田のなまはげを知らない人はいない、と言っても過言ではないほど有名です。そのなまはげの発祥にまつわる鬼伝説には漢の武帝まで登場します。さらに十和田湖の女神を中心に赤神と黒神の戦いがあり、現存する石段にまつわる伝説もあります。
赤神神社 五社堂にはこれほどの伝説や言い伝えが集中しています。いずれも赤神神社の創立から神仏習合、神仏分離を経て、複雑に絡み合い現在へ伝えられてきた言い伝えとも言えますが、現在も存在している赤神神社 五社堂と石段を歩いてみると、厳かな気持ちになることは間違いありません。
赤神神社 五社堂への石段の登り口へのアクセスも比較的しやすい場所にあります。1年を通して表情を変える五社堂周辺の景色を眺めながら、御朱印をいただくためにじっくりと石段を踏みしめての散策や、奥宮までの登山を楽しんでみられるのはいかがでしょうか。
おすすめの関連記事
MORISUK3
人気の記事
-
「磐梯朝日国立公園」は3県にまたがる公園!その範囲や周辺の温泉は?
-
「フルーティアふくしま」でスイーツ&鉄道旅へ!料金や予約方法は?
-
郡山駅周辺のおすすめランチ17選!便利な安いお店や名物料理の人気店も!
-
山形の大判焼き「あじまん」が絶品!人気商品・販売店舗や営業時間は?
-
福島の桜の名所ランキングTOP25!開花&見頃の時期は?穴場まで紹介!
-
新幹線で足湯を満喫!リゾート列車「とれいゆつばさ」を楽しむ方法とは?
-
東北屈指のパワスポ「出羽三山」を参拝&観光!3つの山と神社を巡る!
-
「山形花笠まつり」は夏の伝統風物詩!その歴史や魅力を徹底解剖!
-
「銀山温泉」へのアクセス方法!東京や大阪など主要都市からのおすすめは?
-
山形のゆるキャラグランプリTOP15!多数のキャラクターの頂点は?
-
山形のご当地名物グルメTOP20!絶品の郷土料理やB級グルメとは?
-
山形のおすすめお土産BEST30!人気のお菓子や雑貨などジャンル別に!
-
ハタハタの卵は虹色?その味や食感は?おすすめ料理のレシピも紹介!
-
秋田のご当地ヒーロー「超神ネイガー」とは?人気グッズや歌を紹介!
-
「日本三大奇祭」とは?それぞれの見所や特徴・その他の奇祭まとめ!
-
秋田のローカル線「由利高原鉄道」で列車旅!魅力や撮影ポイントを紹介!
-
秋田名物・稲庭うどんが東京でも食べられる人気店9選!ランキングで紹介!
-
青森「田舎館村」の田んぼアートを鑑賞!見頃の時期や歴史とは?
-
「岩木山神社」は狛犬が珍しいパワスポ!恋愛運&金運UPの人気神社!
-
青森県民の大好物「イギリストースト」とは?種類や味・由来を解説!
新着一覧
-
西のお伊勢さま!「山口大神宮」参拝のご利益や御朱印&お守りをご紹介!
-
米子「とんきん」は地元で圧倒的人気のカレー専門店!人気メニューは?
-
箱根には魅力的なコテージが満載!大人数やカップルにおすすめコテージ16選!
-
岡山の釣りスポットを大特集!人気スポットや穴場スポット16選
-
【岡山発】皮ごと食べられる「もんげーバナナ」はどこで買える?販売店や通販情報を徹底解説
-
【鳥取県】江府町のおすすめスポット15選!人気の観光地や道の駅、ランチやふるさと納税情報も!
-
【聖地巡礼】「千と千尋の神隠し」の舞台やモデルはどこ?油屋&湯屋に似ている旅館10選を紹介
-
岡山のおすすめ鉄板焼きTOP22!高級店が勢揃い!
-
岡山のおすすめキャンプ場20選!デイキャンプやオートキャンプを厳選!
-
岡山のおすすめ温泉20選!露天風呂や日帰り温泉を厳選!
-
漆黒の城「岡山城」の楽しみ方!見どころや御城印がもらえる場所、周辺の観光スポットを徹底解説
-
倉敷の人気うどん屋TOP22!安くておいしい名店が勢揃い!
-
【岡山】美味しい水はここにあり!「塩釜の冷泉」で喉と心を潤そう!周辺のおすすめスポットも解説!
-
千と千尋は四万温泉がモデル!赤い橋や温泉が楽しめる!
-
海のミルク『寄島の牡蠣』を堪能する旅へ!直売所や通販情報も徹底解説!
-
岡山から鳥取の行き方徹底解説!格安で行ける交通手段は?
-
鬼怒川温泉の廃墟群がヤバい!廃墟になった理由とは?心霊現象が起きる廃墟も!
-
暑い夏には岡山へ!おすすめかき氷店20選!桃やピンスの名物も!
-
【市町村別】岡山のおすすめドライブスポット55選!家族・友達・デート・ひとりでも楽しめる楽しい&絶景スポットを紹介
-
【日本三大産地】岡山の牡蠣は大粒でクリーミー!食べ放題や海鮮BBQ、カキオコの人気店全13選&産地直送の人気通販5選!