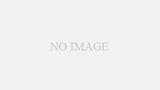2019年11月18日公開
2020年01月23日更新
「口取り菓子」って何?その意味や由来を解説!北海道の正月には欠かせない!
北海道には「口取り菓子」と呼ばれるお正月に欠かせない食べ物があります。北海道と一部地域にだけの定番として有名な「口取り菓子」とはどんなものでしょうか。テレビでも紹介され有名になった北海道特有の「口取り菓子」について、その意味や由来を解説しています。

北海道では有名な「口取り菓子」とは
「口取り」という言葉を茶道やおせち料理などに関係する言葉として耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。
テレビ番組などで紹介され北海道の食文化として有名になったのが「口取り菓子」と呼ばれるもの。本州にも「口取り菓子」と呼ばれるものはありますが、北海道のとは少し意味が変わってきます。
「口取り菓子」は北海道ではお正月に欠かせない縁起物です。北海道の子供たちはお年玉と同じようにこの「口取り菓子」を毎年待ちわびています。この北海道の「口取り菓子」とはどういったものなのか、意味や由来などを解説していきます。
北海道のお正月の大定番!
正月の口取りって青森〜北海道なの??
おせち食べないけど、口取りは必ずあるよね…
スーパーに並ぶとテンション上がってくる(笑)
家にもよるかもだけど
正月はコレと醤油ベースのお雑煮でおわり!!! pic.twitter.com/2MKoqQBjHu— ねこうどん@四葉研究所🍀 (@nekoudon58) November 13, 2019
一般的に「口取り」はおせちなどの本膳料理に添えて出す甘味のある勝栗(くりきんとん)、熨斗鮑、昆布などをお盆に乗せたものを意味しています。
本州とは違った独特の食文化や風習ができてきた北海道で、「口取り菓子」は定番の正月のお菓子を意味しています。口取り菓子は、北海道ではお正月に食べる大定番でコンビニやスーパーマーケットなどどのお店でも必ず見かけるお菓子の一つです。
北海道民はこの口取り菓子は全国的に食べられていると思っている人がほとんどで、他県に移住した人などは正月にこの口取りが売っていないことに寂しさを感じるのだとか。
青森の一部でも
ウェーイ🍺東北ホップ&迎春🐗🎍
口取り〜🐟?←青森で買って来た明日には旦那達帰って来てしまうので、残されたフリーダムな時間は今日限り… pic.twitter.com/2ngwI50KAc
— ありよ🐾 (@ariyo101320) January 1, 2019
北海道はとても有名な「口取り菓子」ですが、青森の一部地域でもこの「口取り菓子」が正月に食べられています。北海道特有と言われている「口取り菓子」は青森の一部地域で正月の定番として家庭に親しまれているようですね。
大晦日の供え物の役割も
口取り菓子
北海道では正月にこういうお菓子をお供えします#ファインダー越しの私の世界 #写真撮ってる人と繋がりたい #写真好きな人と繋がりたい pic.twitter.com/OiHPfUeIB4
— 新一 (@greenbluse) January 10, 2017
本来はおせち料理を神棚や仏壇に挙げてから食べる風習がありましたが、それを簡略化させたものが「口取り菓子」ではないかと言われています。この風習の名残で北海道では「口取り菓子」をまず神棚や仏壇に挙げてご先祖様にお供えします。
おせち料理は豊作などに感謝してその作物で作った料理を神様に供えたのが始まりで、その献立の一つ一つに意味があります。また、その年の幸せを願いながらおせち料理を食すのが正月の風習でした。
関西の恋人の実家…
お雑煮は白。
祝箸というものがある…
(正月三が日は名前の書かれた箸袋に箸を入れる)自分の家以外の他地域で正月を過ごすことってないので面白い😲
北海道とか沖縄とかまた違うのかなぁ? pic.twitter.com/KcHJNkPdCK
— オクユイカ@地域共生福祉を実践中! (@Saba0m) January 2, 2019
祝箸と呼ばれるおせちを食べるための箸は両端の先端が細くなっていて、大晦日には箸袋に名前を書いて神棚に置く風習があります。その箸を使うことで年神様と一緒におせちを食べて縁起を担ぐことができる、ということです。
北海道では「口取り菓子」を神棚に上げるのはこのおせち料理の由来から大晦日にお供えする供え物の役割ではないかとされています。
中身はあんこの練り菓子
【偽くまこ】口取り(くちとり)菓子の中身はこのような形です。あまーーーいお菓子です。この他、さくらんぼや干支、みかん等の口取り菓子があります。 pic.twitter.com/pFvMD5IR
— 森くまこ11/27~12/3迄名古屋名鉄百貨店地下催事にサンタクリームで出没 (@recipe_kumako) December 26, 2011
色々な形に形取られた「口取り菓子」ですが、和菓子の練り切りと同じ素材で作られています。和菓子の練り切りは白あんを練って形を作っています。
かまぼこにも見える「口取り菓子」ですが、本体は白あんで中にこしあんが入っているものもあります。形については後ほどご紹介する定番の形のほかに、羊羹が入っていて全体的に甘いお菓子という印象です。
おせちの合間や食後に食べる
あんこで作られている口取り菓子ですが、おせちを食べる合間のお口直しとして食べたり、食後に食べたりしています。甘くておいしいので北海道の子供たちには特別なお菓子としてケーキなどと並んで人気です。
お茶のお供が定番
北海道の定番として有名なカラフルで見た目も可愛い「口取り菓子」。今では仏壇などに供えたあと、お茶のお供として家族や訪れるお客さんとのお茶の時間にお茶のお供として食べるのが定番となっています。白あんの和菓子ですが優しい甘さでコーヒーや紅茶などにも合います。
北海道の「口取り菓子」定番の形
先程口取りを食べました。
その中に鮭の形をしたものがありました。
見た目は焼き鮭そっくり! pic.twitter.com/O9je6lZfjP— ゆーりん (@k_fm761) December 31, 2016
北海道の子供たちにも人気の「口取り菓子」。このお菓子にはいつの頃からか定番の形が存在します。縁起を担ぐという日本の文化に添った北海道の「口取り菓子」ですが、一般的に売られている「口取り菓子」はどのような形が定番なのでしょうか。
口取り菓子の定番の形①鯛
元旦に買った、六花亭の鯛の形の口取りも忘れてた。 pic.twitter.com/GH3mU3IM90
— 妖怪目玉 (@youkaimedama) January 4, 2019
まず定番の形として上げられるのが「鯛」。縁起物の定番として「口取り菓子」に必ずと言ってよいほど入っているのが鯛の形の「口取り菓子」です。
”おめでたい”という言葉を絡めてお祝いの席でも実際に鯛の塩焼きを食べることもありますが、その紅白の色合いも縁起が良いとされ日本では重宝されている高級魚です。
口取り菓子の定番の形②松竹梅
お雑煮の後の口取り菓子…3人共梅を入れている(☞三☞ ˘ω˘ )☞三☞ pic.twitter.com/7oAC1msnqR
— 😇沙羅😇 (@sara_hjmk) January 1, 2017
定番の形の二つ目は「松竹梅」です。”松”は寒い季節でも枯れない常緑樹として「長寿」の象徴の縁起物とされ、”竹”は地に根を張ってまっすぐに伸び新しい芽をどんどん出すので「子孫繁栄」の縁起物として、梅は「気高さ」の象徴として古来から日本人に愛されてきました。
口取り菓子の定番の形③海老
これは…?
北海道の道南で食される正月縁起物
「口取り菓子」です✨
あんベースの練りきりで作られてます。
鯛と海老にはさらにあんが入るのが定番スタイル。(入ってないのもあり)
ケンミンショーでも取り上げられたことがあるんです〜 pic.twitter.com/Cxxqjx0U1Q— りんご (よくばり民) (@be_there178) December 31, 2016
定番の形の3つ目は”海老”。腰が曲がっても元気でいる姿から「腰が曲がるまで丈夫で元気でいられるように」と願いが込められた縁起物です。おせち料理に海老が入っているのも長寿の願いがこもっています。
口取り菓子の定番の形④干支
北海道ではお正月に、口取りと言ってお正月にちなんだ形の和菓子を食べるのですが…(鯛とか海老とか来年の干支が多い)
今年は干支全種類うってて、卯と虎を迷わず購入です! pic.twitter.com/wbnO6i4XaV— めい (@ari2679) December 26, 2016
定番の形四つ目は「干支」。やはりお正月の縁起物のお菓子なので干支が加わります。自分自身の干支をお守りやお札などを見につけると「無病息災・厄除け」として縁起が良いとされています。
ほかに家庭に飾っておくと「家内安全」、人に授けると「招福祈願」や「安寧長寿」をもたらす物としてその縁起を担ぐとされています。お店では十二支揃って売っていることもあるそうです。
「口取り」の意味・由来
「口取り」の似たような言葉を探すとすれば、「口直し」でしょうか。ただ実は、「口取り」の由来はよくわかっていないそうです。「口取り」という言葉はかなり昔からあるそうですが、江戸時代以前からあるというのがわかっているだけで由来はわからないといわれています。
北海道は色んな地域の文化が集まってミックスされ、環境の中で簡略化されていることも多く、「口取り」もそんな状況からから生まれた由来があるのではないかとという説もあるのだそうです。
「口取り」の由来は口取り肴から
今年はおせち作れそうにない。コレは去年のです。去年は犬が術後で 私も家から出なかったから全て手作りできた。楽しかったなぁ~🎵
筑前煮・紅白蓮根・八幡巻き・ローストビーフ・林檎のワイン煮(クリチサンド・生ハム巻) ・桜なます・紅白なます・松前漬け・ナッツごまめ・
伊達巻と黒豆は入らず💧 pic.twitter.com/Jgyh9dr1lU— noa* (@naosan9) December 28, 2017
「口取り」の由来ははっきりとはわかっていませんが様々な説がこの「口取り」という言葉にはあります。有名なところでは「口取り」の由来のひとつに、「口取り肴」という言葉があがります。
口取り肴とは
「口取り肴」とは、正月に訪れたお客さんにおせち料理を出す前のお酒のおつまみとして昆布や勝栗、かまぼこ、ごまめなどを盛り合わせたものを指します。一般的には奇数が縁起を担ぐとされていて、「口取り肴」は3品~9品の奇数の品数を盛り合わせています。
北海道の地酒のおすすめはこちらでチェック!
一般的な「口取り菓子」の意味
「口取り菓子」というと、北海道ではお正月に食べる縁起物の形をしたお菓子のことを指します。本州にももちろん「口取り菓子」という言葉が存在しますが、北海道以外の地域では「口取り菓子」は茶道のお茶のお供に出すお盆に乗った和菓子のことを意味しています。
おせちの代用品だったとの仮説が!
北海道に来てから「口取り」っていうおせち料理みたいな和菓子の詰め合わせを沢山見かけるんだけど、関東もこういうのってあったっけ pic.twitter.com/Y0iflMch7m
— 中島 (@risugoya) December 28, 2013
おせち料理はそもそも新しい年と迎える際に、神様にお供えする料理でした。おせち料理を模して作った縁起物の鯛や海老の形をしているお菓子をおせち料理の代用品として神棚に上げたという仮説もあるそうです。
北海道内で口取りが買える場所!
北海道ではどのこの商店でも「口取り菓子」を購入することができます。クリスマスが終わると一斉に店頭に並びだし、山ほど積み上げている売り場もあるほどです。
口取りが買える場所①スーパー
この季節になるとスーパーで売っている大好きな口取り菓子(和菓子)😊🍒
なのに今年はまだ買えてない~😅
なかよし(@torakko222)さんに触発され食べたくて仕方がない😝💨https://t.co/DWPEybeyB3
(↑口取り菓子について)
※画像お借りしました。 pic.twitter.com/JhI9dEZPpZ— ふくねこ (@opafu) December 29, 2018
北海道のスーパーマーケットとして有名なのがコープをはじめラルズやラッキー。北海道に根差した地域密着型のスーパーです。このほかにも北海道のどのスーパーでも口取りが販売されています。
口取りが買える場所②コンビニ
今年のセコマは正月休む pic.twitter.com/RJS6Sadpuc
— すみす (@smith__227) December 31, 2017
北海道のコンビニといえば、セイコーマート!道民が愛するコンビニの大手はもちろん、他のコンビニエンスストアでも口取りは販売されます。
口取りが買える場所③和菓子店
出店情報です!
12月29日(金)〜1月3日(水)
ウィングベイ小樽1F
イオン横 ハイタッチコート口取り 栗きんとん 豆きんとん等
お正月商品 取り揃えてます。 pic.twitter.com/5WNVpdisrT— 和菓子処 つくし牧田 (@tsukushimakita) December 27, 2017
口取りは和菓子なのでもちろん和菓子屋でも購入できます。豪華なものになるとおせち料理のようにお重に入った「口取り菓子」も販売されているのだとか。
また、和菓子屋ならではの技術で定番の形以外の口取りも販売されています。可愛いらしい口取りは食べるのが勿体ないと感じてしまうほどです。札幌の人気和菓子店はこちらでご紹介していますので併せてご覧ください。
口取り菓子は北海道特有の食文化!
口取りは北海道にしかないって聞いてショックだったな。甘すぎて好きではなかったけど、可愛いいから。 pic.twitter.com/YP2ck3LokU
— 結城花音@12/1ふりまde和空間 (@yuukikanon42) July 26, 2019
北海道では超定番の正月のお菓子「口取り菓子」。北海道特有の食文化としてテレビ番組でも紹介され、他の地域でも有名になってきました。
お正月限定で食べられるお菓子としてスーパーに習う様子は本州ではなかなか見られない独特の風景です。その数も膨大で旅行の土産話にもきっといい話題になるのではないでしょうか。ぜひお正月時期に北海道に訪れた際にはこの「口取り菓子」をお試しください!
おすすめの関連記事
ぶんゆみ
人気の記事
-
函館&郊外の花火大会特集!夏の風物詩を満喫!開催日程や時間まとめ!
-
函館八幡宮の御朱印やお守りを紹介!初詣や結婚式に人気のスポット!桜も!
-
【札幌】サッポロビール園を堪能!大人の旅にジンギスカンとビールがおすすめ!
-
【閲覧注意】札幌の驚愕心霊スポット13選まとめ!恐ろしい心霊物件も?
-
函館空港から函館駅までのアクセスまとめ!バス/電車/タクシーの料金は?
-
「札幌市時計台」はがっかり名所ではない!日本最古の時計塔の魅力とは?
-
函館のご当地名物グルメ15選!地元民も御用達の必ず食べたい料理とは?
-
札幌のロマンチックな夜景が見えるレストラン15選!デートや記念日に!
-
函館山に車で行くには?周辺駐車場やアクセスを徹底解説!混雑状況も!
-
子供が喜ぶ!札幌のアスレチックが楽しめる公園13選!大人も一緒に!
-
さっぽろ雪まつりは氷と雪の芸術祭典!有名な雪像は圧巻!日程や場所は?
-
札幌の動物園&水族館3選!子供やカップルにもおすすめスポット!
-
明日風公園は遊具が充実!巨大ジャングルジムや滑り台が人気!夏は水遊びも!
-
札幌初夏の風物詩!YOSAKOIソーラン祭りの見所!2020の開催日程は?
-
札幌のおすすめ日帰り温泉&スーパー銭湯12選!露天風呂や天然温泉まとめ
-
北海道神宮の無料&安い駐車場一覧!料金や場所まとめ!混雑時間は?
-
札幌の室内&子供遊び場27選!雨や冬の寒い日におすすめ!無料スポットも?
-
札幌屈指の桜の名所「円山公園」!周辺の観光&グルメ情報も!まるで秘境?
-
北海道神宮の六花亭「判官さま」は名物限定メニュー!無料で食べられる?
-
モエレ沼公園のアクセス&駐車場情報まとめ!バスはある?駐車場料金は?
新着一覧
-
西のお伊勢さま!「山口大神宮」参拝のご利益や御朱印&お守りをご紹介!
-
米子「とんきん」は地元で圧倒的人気のカレー専門店!人気メニューは?
-
箱根には魅力的なコテージが満載!大人数やカップルにおすすめコテージ16選!
-
岡山の釣りスポットを大特集!人気スポットや穴場スポット16選
-
【岡山発】皮ごと食べられる「もんげーバナナ」はどこで買える?販売店や通販情報を徹底解説
-
【鳥取県】江府町のおすすめスポット15選!人気の観光地や道の駅、ランチやふるさと納税情報も!
-
【聖地巡礼】「千と千尋の神隠し」の舞台やモデルはどこ?油屋&湯屋に似ている旅館10選を紹介
-
岡山のおすすめ鉄板焼きTOP22!高級店が勢揃い!
-
岡山のおすすめキャンプ場20選!デイキャンプやオートキャンプを厳選!
-
岡山のおすすめ温泉20選!露天風呂や日帰り温泉を厳選!
-
漆黒の城「岡山城」の楽しみ方!見どころや御城印がもらえる場所、周辺の観光スポットを徹底解説
-
倉敷の人気うどん屋TOP22!安くておいしい名店が勢揃い!
-
【岡山】美味しい水はここにあり!「塩釜の冷泉」で喉と心を潤そう!周辺のおすすめスポットも解説!
-
千と千尋は四万温泉がモデル!赤い橋や温泉が楽しめる!
-
海のミルク『寄島の牡蠣』を堪能する旅へ!直売所や通販情報も徹底解説!
-
岡山から鳥取の行き方徹底解説!格安で行ける交通手段は?
-
鬼怒川温泉の廃墟群がヤバい!廃墟になった理由とは?心霊現象が起きる廃墟も!
-
暑い夏には岡山へ!おすすめかき氷店20選!桃やピンスの名物も!
-
【市町村別】岡山のおすすめドライブスポット55選!家族・友達・デート・ひとりでも楽しめる楽しい&絶景スポットを紹介
-
【日本三大産地】岡山の牡蠣は大粒でクリーミー!食べ放題や海鮮BBQ、カキオコの人気店全13選&産地直送の人気通販5選!