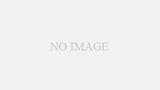伝統工芸品「曲げわっぱ」とは?お弁当箱に人気の種類や特徴を解説!
秋田県大館市の「大館曲げわっぱ」は、木のぬくもりが美しい日本が誇る伝統工芸品です。木が持つ吸湿効果で冷めたごはんも美味しく食べられると、お弁当箱に人気です。レンジが使えないなどのデメリットがありますが、曲げわっぱにはそれ以上のメリットがあるのが魅力です。

目次
曲げわっぱとは
「曲げわっぱ」とは、杉やヒノキなどの薄い板を曲げて作る蓋つきの箱のことです。お弁当箱などとして人気があります。曲げわっぱに代表される曲物は、全国各地の工芸品として作られてきました。その中でも、秋田県大館市の「大館曲げわっぱ」が有名です。
曲げわっぱは薄い板を独自の技法で曲げ、つなぎ目を桜の木の皮でとめます。漆などを塗らない大館曲げわっぱは、木目の色合いや模様、曲線の美しさで人々を魅了しています。大館市には体験ができるメーカーもあり、とても人気があります。
日本に古くから伝わる伝統工芸品
大館市の伝統工芸品「大館曲げわっぱ」。
弾力性があり、美しい木目を特徴とする秋田杉を使った工芸品です。
大館市の「#わっぱビルヂング」では、曲げわっぱのギャラリーや制作体験を楽しめます。https://t.co/8o7Qz9klyS pic.twitter.com/KoBdjhFwDl— あきたびじょん (@akitavision) November 15, 2019
曲げわっぱに代表される曲物は、古くから日本各地でつくられてきた伝統工芸品です。地域によって、呼び方が異なります。秋田県大館市の曲げわっぱをはじめ、青森県の「ひば曲げ物」、漆を塗る静岡県の「井川メンバ」などが有名です。
中でも「曲げわっぱ」という呼称は全国的にも有名で、大館曲げわっぱは古い歴史などから国の伝統的工芸品に指定されています。お弁当箱やおひつをはじめとして、コップや菓子器、ごみ箱や小物入れなどに使える種類もあります。
主に米びつやお弁当箱として使用
ご飯炊くのに炊飯器を使わなくなってからずっとおひつが欲しかったんやけど、このたび秋田県の大館の曲げわっぱのおひつを我が家にお迎えすることになりましてとても嬉しい。細部に職人さんの魂が宿っている。とても滑らか。美しい。大事に大事に使うっっ! pic.twitter.com/LRmfkRBymW
— フリーダムともこ復活! (@tommokoir) August 31, 2019
曲げわっぱは通気性や保湿性に優れていて、米びつや手軽なものではお弁当箱として使用されます。特に曲げわっぱのお弁当箱は、吸湿効果によってごはんが美味しくなると評判です。ひとつめの曲げわっぱとしても気軽に使えます。
丸い形のお弁当箱は、四角いものより詰めやすく見た目もかわいいと人気があります。そんな丸いお弁当箱を愛用している人たちにも曲げわっぱはとても人気です。電子レンジが使えないなど不便な点もありますが、冷めてもごはんが美味しいのでレンジは必要ないとの声も多数あります。
全国の曲げわっぱの産地
杉やヒノキを使ってつくる伝統工芸品「曲物」は、秋田や青森などの東北地方が有名ですが、ほかにも九州など全国各地でつくられています。地域によって「曲げわっぱ」、「メンパ」など呼び方が異なり、漆が塗られた種類もあります。
日本の曲物に使われる木材は杉やヒノキが主で、青森では青森ヒバなど地域のものや、木の性質や特徴によって種類が使い分けられています。
①秋田県大館市「大館曲げわっぱ」
大館郷土博物館の特別展示室では「日本各地の曲物と大館曲げわっぱ」を展示中です。#大館曲げわっぱ はもちろん、全国の色々な曲物をご覧いただけます。
大館市はうっすらと雪が積もり寒いです! ぜひ暖かい服装でお越しくださいませ。
【歴史文化課】 #大館市 #工芸 #曲物 #大館郷土博物館 #秋田県 pic.twitter.com/5YvaQMlAqe— 秋田県大館市 (@odate_city) December 1, 2019
曲物の中でも有名な「大館曲げわっぱ」は、天然の秋田杉を使用しているため香りがよいのが特徴です。調湿効果に優れ、詰めたごはんが美味しくなることや、美しい木目や色合いなど見た目にも高級感があります。
曲げわっぱは木材でできているため、湿気や熱湯に弱いなどの特徴もあり、手入れには注意が必要です。しかし、手入れも難しいものではなく、少し気をつけて正しい手入れをするだけで長く使用することができます。
国の伝統工芸品に指定
大館の伝統的工芸品「曲げわっぱ」。秋田杉で作るから、お米を入れると風味が引き立つ!!杉の香りと共に食べるあきたこまち(秋田ブランド米)はまあうめすな。本当に美しい工芸品だと思います。お弁当箱から食器までなんでもできる。大館では体験工房もやってます!職人になる若者増えるといいなあ。 pic.twitter.com/SQN2oZQzxY
— [大サワ 館まる]秋田県大館市紹介アカウント!🐕 (@Osawadatemalu) November 10, 2017
曲げわっぱは、1980年に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されました。国の伝統的工芸品に認められるのに必要な年数には「100年以上の歴史があり、現在も継続しているもの」とされています。
また、日常生活に取り入れられているもの、手作業でつくられていること、一定の地域で生産されていることなどの条件もあります。
②青森県藤崎町「ひばの曲物」
お昼ごはん
おNEWの曲げわっぱ🎶
昨日お小遣いで買っちゃった😁
今日もガパオ炒めのっけ弁当だよ#摂食障害#摂食障害克服中 #拒食症克服中 pic.twitter.com/DO9EX91EV0— コン (@bagel_charo) December 2, 2019
青森県津軽地方の伝統工芸品「ひば曲げ物」は、見た目は大館曲げわっぱと似ていますが、こちらは青森ヒバでつくられています。ひば曲げ物は耐久性に優れ、水分が滲みにくいことが特徴です。県の伝統工芸品に指定されています。
現在、ひば曲げ物をつくる職人は青森県藤崎町に住む男性ただひとり。以前は津軽地方の各地にいた職人もプラスチック製品が主流になってきたことにともない減少、今では最後の職人として「ひば曲げ物」をつくり続けています。
③静岡県静岡市「井川メンパ」
母方の祖母の形見分けで譲ってもらった井川メンパ
森竹は祖母の旧姓 pic.twitter.com/hKMuilWkYh— Air (@77tmair) May 26, 2018
静岡県でつくられる「井川メンパ」。曲げわっぱとの違いは、漆が塗られていることです。天然漆の光沢が美しく、板のつなぎ目は漆で固められているため耐久性もあるので、漆を塗り直して何年にもわたって使い続けられます。
漆が塗られている井川メンパは、汁物を入れてもこぼれません。井川地区では修理をしたり漆の塗り直しをしながら、家に受け継がれる井川メンパを代々大切に使っています。井川メンパの職人も、現在ではお一人しか残っていないそうです。
④長野県塩尻市「木曽奈良井宿の曲物」
今日も茶色いだけの弁当
葉ごぼうもマンバ(高菜の仲間)もそろそろ終わり娘とお揃いで買った曲げわっぱ
社会人一年生さん、頑張ってお弁当まで作れてるかな?#曲げわっぱ #わっぱ弁当 #奈良井宿 pic.twitter.com/yezOCl7OfN— しっぽな (@sippona3) April 18, 2018
長野県塩尻市にある奈良井宿の曲物は、木曽のヒノキやサワラの木が使われます。奈良井宿ではお土産にも人気です。静岡の井川メンパと同じように、漆が塗られているのが特徴です。軽くて丈夫で、お弁当箱が人気です。
漆などの塗装がされている種類は、白木同様に電子レンジや食洗機は使えませんが、洗うときなどに白木のものより手入れが楽という特徴もあります。
⑤三重県尾鷲市「尾鷲わっぱ」
最近お弁当を持って行くようになり、お弁当箱が欲しくなったので、尾鷲の「ぬし熊」さんで尾鷲わっぱの弁当箱を買いました(*’▽’*)職人さんが一人になってしまったそうで、凄く美しいわっぱなのに残念です><修理とか、塗り直しとかお願いしたいので末永く頑張って続けて欲しいですね。 pic.twitter.com/7LNUFOOkwr
— もっちー (@K_Mochy) September 8, 2018
上質な尾鷲ヒノキを使用した三重県の「尾鷲わっぱ」。天然の漆にこだわり、使い込むほどに深い味わいが出ます。尾鷲わっぱも修繕や漆の塗り直しも可能なので、手入れをしながら代々受け継ぎ長く愛用できます。
⑥福岡県福岡市「博多曲物」
博多にも曲げわっぱがあると知り、博多曲物の「柴徳」さんへ。コーティングのない素の杉材を使った、素朴な一段の弁当箱をもとめる。少し手間はかかるけど、木の香りがごはんに移って美味しいはず♪
#曲げわっぱ #まげわっぱ #博多曲物 pic.twitter.com/wkmuKFxlcv
— tomo (@Tokyo_NorthLife) March 2, 2016
「博多曲物」は、大館曲げわっぱや青森のひば曲げ物のように漆を塗らない曲物です。祭祀の道具などにも使われてきた歴史があります。お弁当やおひつのほか、箸入れや角形のものもあります。博多曲物は、華やかな絵つきの種類があるのも特徴です。
大舘曲げわっぱの歴史と人気ブランド
大館の曲げわっぱにはとても古い歴史があります。盛んに作られるようになったのは江戸時代ですが、奈良時代には曲げわっぱの原型になるものができていたといわれています。昔からの伝統を大事にした大館曲げわっぱは、国の伝統的工芸品に指定されています。
近代では各メーカーで伝統の曲げわっぱをはじめ、新しいモダンなデザインを取り入れた曲げわっぱを作るなど、よいものを残しながら時代の変化に合わせた曲げわっぱ作りもされています。
大館曲げわっぱの歴史
大館曲げわっぱのお弁当箱
曲げわっぱは杉材の美しい柾目部分を薄く剥ぎ、熱湯につけて柔らかくしたものを型に合わせて素早く曲げて乾燥し、桜皮で縫い留め、底面を隙間のないようにはめ込み完成させます。
最近は弁当箱だけでなくカップや酒器なども人気。
すべて職人による手仕事で作られています。 pic.twitter.com/6o0tfDLQAL— しまぬき (@shimanukikokesi) April 3, 2018
秋田の伝統工芸品「大館曲げわっぱ」の始まりは、奈良時代にマタギが作った杉の木を曲げて桜の皮でとめた弁当箱のようなものとも言われています。大館で曲げわっぱが盛んに作られるようになったのは江戸時代です。
関ヶ原の戦いでに敗北した豊臣方の武将・佐竹義宣が水戸から秋田へ移転させられた頃、秋田の人々の暮らしはとても困窮していました。大館城主となった佐竹西家は、領内の豊富な秋田杉を利用した曲げわっぱ作りを下級武士たちの内職として推奨しました。
大館曲げわっぱの作り方
昨日デパートの職人展にて
柴田慶信商店の
大館曲げわっぱを購入◎ずっと欲しかったので
伝統工芸士の実演販売に
迷わず夫と二人分お願いしました( ¨̮ )秋田杉の良い香りと
美しい造形にうっとり♡ pic.twitter.com/tGqSqaiwZI— moi* (@momonohananoki) March 25, 2016
大館曲げわっぱは、まず板を煮るところから始まります。前日のうちに水に入れておき、十分に水を吸わせておくと中まで熱がとおり曲げやすくなるそうです。その板を丸太に沿って巻くようにして曲げていきます。その後一週間から10日かけて乾燥させます。
そしてつなぎ目を接着してまた丸一日置き、底板をはめこんだりして曲げわっぱが完成します。曲げわっぱ本体や蓋も、出っぱりが少しでもあればやすりなどで削り、美しい曲げわっぱができます。
大館曲げわっぱの人気ブランド
大館の伝統的工芸品「曲げわっぱ」。秋田杉で作るから、お米を入れると風味が引き立つ!!杉の香りと共に食べるあきたこまち(秋田ブランド米)はまあうめすな。本当に美しい工芸品だと思います。お弁当箱から食器までなんでもできる。大館では体験工房もやってます!職人になる若者増えるといいなあ。 pic.twitter.com/SQN2oZQzxY
— [大サワ 館まる]秋田県大館市紹介アカウント!🐕 (@Osawadatemalu) November 10, 2017
秋田県大館市内には、数々の曲げわっぱのメーカーがあります。どのメーカーでも代々受け継がれてきている伝統を重んじた曲げわっぱ作りを大事にするとともに、新しいデザインなども積極的に取り入れています。
曲げわっぱメーカーの中には、工場見学や制作体験ができる工房もあります。曲げわっぱ作り体験では、作り方を丁寧に指導してもらえるので、しっかりとした曲げわっぱを作ることができます。体験で自分の手で作った曲げわっぱのお弁当など、日々の暮らしが豊かになるアイテムが手に入ります。
①柴田慶信商店
柴田慶信商店さんでお買い物。丸い子がずっと欲しかったの~♪9月頑張った自分へのご褒美。杉の香りに癒やされてる(´•᎑•`) pic.twitter.com/JvhUA6YnCZ
— akiko yoshida (@akyos60) September 29, 2019
「柴田慶信商店」は、JR大館駅から徒歩でも行ける距離にある人気の曲げわっぱブランドです。独学で曲げわっぱの製作を始めた初代から受け継がれる技術や技法で、丁寧な曲げわっぱ作りがされています。
柴田慶信商店では、曲げわっぱの制作体験ができます。制作体験では丸型のお弁当箱と18cmのパン皿が選べます。本格的な道具を使った曲げわっぱ作りを体験することができます。
| 名称 | 柴田慶信商店 |
| 住所 | 秋田県大館市御成町2丁目15-28 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| アクセス | JR大館駅より徒歩6分 |
| 公式HP | http://magewappa.com/ |
②大館工芸社
ずっと欲しかった丸二段重。いいにおい♡ 大館工芸社さんの曲げわっぱお手入れもしやすくて好き。 pic.twitter.com/zGDqt3GnRD
— ユウ (@bambimomo33) May 23, 2019
「大館工芸社」では、曲げわっぱの製造工場を見学することができます。職人がおこなう曲げから桜皮縫などが間近でみられます。大館工芸社でも、曲げわっぱの制作体験ができ、同時に曲げわっぱの伝統や制作技術、手入れなどについても学べます。
| 名称 | 大館工芸社 |
| 住所 | 秋田県大館市釈迦内字家後29-15 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| アクセス | JR大館駅より車で6分 |
| 公式HP | http://www.magewappa.co.jp/ |
③栗久
精米機を買って羽釜でご飯を炊くようになって7〜8年経つ。
おひつは必須。
ずっとこのおひつが欲しかったけど安価な物で我慢してた。
でももう炊飯器に戻ることは無いと確信したのでとうとう買った!
「栗久の曲げわっぱ」😆 pic.twitter.com/jUydwVDzY1— 浅野ゆかり (@Yukari_DMC) September 24, 2019
人気の曲げわっぱメーカー「栗久」は、伝統的なもの以外にも、モダンでおしゃれな曲げわっぱが多いのが魅力です。新しい形の曲げわっぱの数々は、グッドデザイン賞やロングライフデザイン賞を受賞しています。日本各地での実演販売もおこなっています。
| 名称 | 栗久 |
| 住所 | 秋田県大館市字中町38 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| アクセス | JR大館駅より車で8分 |
| 公式HP | http://www.kurikyu.jp/ |
大館曲げわっぱの製作体験も
そんなわけで朝はこれ、曲げわっぱ体験してました。
楽しかった! pic.twitter.com/6GzFdGD5wG— ごまめ (@poru_kusu) October 8, 2018
大館市内の曲げわっぱメーカーでは、制作体験ができるところがあります。先に紹介した柴田慶信商店や大館工芸社などで、お弁当箱やパン皿などが作れます。本格的な道具を使用して、丁寧に教えてもらいながら曲げわっぱの制作体験をすることができます。
大館曲げわっぱ協同組合の「大館曲げわっぱ体験工房」は2019年3月に閉館してしまいましたが、問い合わせをすると市内の体験ができる工房を紹介してもらえます。自分で作った曲げわっぱは、さらに愛着が湧く一品になります。
曲げわっぱがお弁当箱に人気の理由
手軽に使える曲げわっぱのお弁当は、曲げわっぱを初めて使う人にも人気があります。曲げわっぱのお弁当の一番の特徴は、木の調湿効果によりごはんがべちゃっとせず冷めても美味しいことです。日本人にとって冷めたごはんが美味しいというのは、お弁当箱として最大の魅力です。
そのため、電子レンジが使えなくてもお弁当が美味しく食べられる、一度曲げわっぱを使ったらプラスチックのお弁当箱には戻れないという曲げわっぱ愛用者が多数です。丸い形や楕円形が特徴の曲げわっぱは、おかずが詰めやすいのも人気の理由です。
理由①軽量で持ち運びやすい
曲げわっぱ弁当箱、最高ですね!
軽いし、メシが美味いし。。
👇で名入りサービスhttps://t.co/wubeCaHaV2 pic.twitter.com/LANHMN21sz— あきえまお (@50sAgency) February 21, 2019
曲げわっぱの魅力のひとつは軽さです。曲げわっぱのお弁当箱はサイズの種類もさまざまで、一段のものや二段のものなどがあります。一段のお弁当箱なら重さは100gほどで、中身を詰めて持ち歩いても苦にならない重さです。
理由②ご飯が美味しい
朝は炊きたてをいただき、1日のエネルギーに。お昼用に炊きたてのまま、曲げわっぱに入れておくと、冷めてもおいしいごはんに。ゆっくり冷ましたごはんはレジスタントスターチが増え、吸収のおだやかな糖になってカロリーにもなりにくくなります。おいしく、健やかな食事の方法です。 pic.twitter.com/iy36KIRU2m
— ykazu(カズ) (@ykazukitchen) October 11, 2019
曲げわっぱは天然の木でできているので、木の調湿効果によって詰めたごはんの余分な水分を吸収してくれます。そのため、ごはんのちょうどよい状態が保たれます。お弁当の冷めたごはんでもべちゃっとすることなく、美味しく食べられます。
これは曲げわっぱが、おひつとして使われることからもわかります。漆が塗られていない曲げわっぱの方が高い調湿効果が期待できます。また、木の殺菌効果によって、夏場でも詰めたごはんやおかずが傷みにくいという特徴も人気の理由です。
理由③見た目が美しい
年末にふるさと納税した時の秋田県大館市の曲げわっぱがやっと届いた〜。
秋田杉の香り漂う木目の美しい曲げわっぱ。大切に使います( *´艸`) pic.twitter.com/bSIBVzaYfy— ぺちこC▲MP (@tacco0111) April 12, 2018
伝統工芸品の曲げわっぱの魅力は、見た目の美しさです。手作業でつくられる美しい曲線や、天然の木目やあたたかい色合いが特徴です。曲げわっぱのような丸い形のお弁当箱は、おかずを多少適当に詰めてもきれいに見えると人気が高まっています。
日本人のすばらしい技術でつくられるお気に入りの曲げわっぱで、毎日のお弁当生活が楽しくなります。大館市内にある工房の制作体験などで作った曲げわっぱなら、さらに愛着がわき、作る楽しみがぐっと増えます。
理由④香りが良い
秋田県の杉を使い、秋田県の伝統工芸品「大館曲げわっぱ」を製造する「りょうび庵」の「曲げわっぱ」。
無塗装仕上げなので秋田杉ならではの香りや、吸湿性・調湿性も存分に実感できます。
姿美しい弁当箱は、普段使いはもちろん、特別な日のピクニックにもぴったりです。https://t.co/EEwCUA3A03 pic.twitter.com/hnVqn62EKu— cotogoto コトゴト (@cotogoto_jp) March 16, 2019
曲げわっぱのお弁当箱は、開けたときなどに香る木の香りも特徴です。ほのかな木の香りがごはんに移り、美味しく食べられます。香りが移るといっても強烈な香りではないので、気になるほどではありません。
曲げわっぱはレンジで使える?
【BENTO bot】
☆ 焼き鮭
☆ 蓮根のキンピラ
☆ 卵焼き
☆ 日の丸御飯#曲げわっぱ pic.twitter.com/wysvyB3dGi— shiba (@shibayama14) December 2, 2019
職場などで食べるお弁当は電子レンジであたためてからという人も多いですが、曲げわっぱは基本的に電子レンジや食洗機は使えません。曲げわっぱは木でできているので、レンジで加熱すると木の中の水分が蒸発し、変形したり焦げる恐れがあります。
通販などでは電子レンジ対応の曲げわっぱも販売しているようですが、大館曲げわっぱは冷めたごはんも美味しく食べられるので、電子レンジであたため直さなくても良いというのが愛用者の感想として寄せられています。
曲げわっぱの塗装の種類
大館の曲げわっぱは、木そのもので無塗装の白木が伝統的な種類です。曲げわっぱの特徴である木目や色合いがとても美しい伝統工芸品ですが、近年では時代の変化やお弁当といった使用方法により、漆塗りやウレタン塗装がされている種類も増えています。
漆塗りの種類やウレタン塗装がされた種類の曲げわっぱは、白木より扱いや手入れが簡単というメリットがあります。一方で、木の香りがしなかったり、曲げわっぱの魅力である吸湿効果がなくなってしまうというデメリットもあります。いずれもレンジや食洗機の使用は厳禁です。
①白木(無塗装)
1月に予約していた「曲げわっぱ・白木弁当箱」本日受け取りました〜💕
マイ曲げわっぱ🎶 pic.twitter.com/smNAJKrE8d— 久田@金森式ダイエット進行中 (@kyudenpara) June 12, 2016
伝統の白木の曲げわっぱとは、天然杉でつくった曲げわっぱに漆やウレタンなどの塗装を施さないものです。木が持っている調湿効果や殺菌効果、香りなどが最大限に生かされるため、お弁当箱やおひつなどに最適です。
塗装がされていないので、おかずの油染みなどが気になりますが、正しい手入れをすることで長く愛用することができます。使い込むうちに、だんだんと色合いが変化していくのも魅力です。曲げわっぱの美しさが一番よく現れるのが白木の曲げわっぱです。
白木のメリット・デメリット
🍱
✨曲げわっぱ✨
.
杉の香りが移って
残りご飯でも、
美味しい😋?
.
手入れも
思ったより楽だし、
無塗装にして良かった。
.#お弁当 #栗久 #わっぱ弁当 #お昼ごはん #lunchbox pic.twitter.com/0k3yvqdaFc— しまゆき (@shimataniyuki) May 26, 2019
塗装を施さない白木の曲げわっぱのメリットは、木が持つ本来の吸湿性や殺菌効果が得られることです。漆やウレタンで覆わないので、杉の香りも感じられます。見た目も木の色合いがそのままで美しいのが魅力です。
デメリットとしては、お弁当箱として使用する場合におかずの油や醤油などの染みがつきやすいことや、正しい手入れをしないと黒ずみが発生したり曲げわっぱ自体が歪んでしまったりすることがあります。
白木のお手入れのポイント
曲げわっぱの弁当箱、密閉できないし手入れめんどくさいのに欲しがる人いっぱいいる理由がわかった。なんてことないおかずでめちゃくちゃ映える。 pic.twitter.com/F7iv5Qpsu2
— たら (@biiruoishiine) August 13, 2019
白木の曲げわっぱの手入れは、お弁当箱の場合はまずお湯を張って汚れを浮かせます。汚れが十分に浮いたらスポンジなどで洗います。家庭用中性洗剤の使用ができない商品もあるので、注意が必要です。
洗ったら自然乾燥で完全に乾かします。職場などでお弁当を洗うと半乾きになってしまうので、帰宅してから洗うのがおすすめです。乾燥には丸一日かかるので、ふたつのお弁当箱を使い分けるか一日おきに使用することで、曲げわっぱがさらに長持ちします。
②漆塗り
今日は、漆塗りの曲げわっぱ持って屋島をフィールドワーク#高松 #香川 #takamatsu #kagawa #uptak pic.twitter.com/QdPmLJ5CuI
— you sakana (@yousakana) November 24, 2019
大館曲げわっぱの特徴を最大限に生かせるのが伝統的な無塗装の白木ですが、メーカーによっては用途や要望によって漆やウレタン塗装の加工をしています。白木は木目や木本来の色などが出るため美しさがありますが、漆塗りの曲げわっぱはきれいな光沢や白木のものより丈夫なのが特徴です。
漆塗りのメリット・デメリット
曲げわっぱ+漆塗りのお弁当箱
ずっと悩んでてやっと購入、そして1ヶ月経過したのだけど想像以上に優れものすぎて…!!
木のお弁当箱、何を入れても美味しそうに見えるし、どんな風に詰めてもおしゃれに見えるし、匂い移らないし洗うのも楽チン! pic.twitter.com/Nvnxf2y3nU— くみこ (@w314rkr) June 1, 2015
漆塗りの曲げわっぱのメリットは、つなぎ目が漆で固められているので無塗装のものより丈夫という点があげられます。天然の漆にも抗菌作用があります。白木の曲げわっぱよりも強度が増し、油染みもできないので扱いが楽になります。
白木の曲げわっぱに比べ、漆塗りのものは木の香りがせず、使い始めには漆特有の臭いが気になることがあります。漆の臭いは、数日陰干しをするなどで解消できます。
漆塗りのお手入れのポイント
届いた!届いたよ!曲げわっぱ漆塗りサビ止めが届いたよ (੭ु ˃̶͈̀ w˂̶͈́)੭ु⁾⁾ pic.twitter.com/m3OAgg5Cdw
— さとみゆ(*´꒳`*)。 (@sat_jul) June 12, 2014
漆塗りの曲げわっぱは中性洗剤で洗えるので、お弁当箱として使用する際にも扱いが楽です。しっかりと乾燥させて乾拭きをすると、漆のつやが増し、経年による色の変化などを楽しめます。電子レンジや食洗機の使用はできません。
基本的にはほかの食器類と同じような使用法、洗浄方法で問題ありません。直射日光にあて続けたり、レンジなどを使用しなければ、長く愛用することができます。漆は塗り直しもできます。
③ウレタン塗装
秋田杉でつくられた「大館工芸社」の曲げわっぱ「小判弁当」。
ウレタン仕上げなので、油染みや色移りの心配もなく、洗うときには洗剤を使えるのも、曲げわっぱ初心者には助かります。
細かな木目の美しさや杉の爽やかな香りは、しっかり楽しめるのが嬉しいです。https://t.co/Yt4hzWx3Ah pic.twitter.com/Bj8ZRxcvF8— cotogoto コトゴト (@cotogoto_jp) May 19, 2018
表面を樹脂でコーティングするウレタン塗装は、見た目のきれいさや汚れにくいのが特徴です。漆のように色がないので、見た目は白木の曲げわっぱとほとんど変わりません。内側にウレタン塗装がされているものは、機能的にはプラチックのお弁当箱と同じです。
ウレタン塗装のメリット・デメリット
食べ終わった🍱
お見苦しい画像を失礼。
曲げわっぱの弁当箱
ご飯詰める時さっと濡らして布巾で拭いて…ご飯粒付かないのよね。
こんな事にも感動。しかし、このお弁当箱はウレタン塗して有るのだ。もう一つ白木の曲げわっぱの弁当箱欲しいなぁ😌 pic.twitter.com/O89Jg1S9Cs— うきたん (@kirikiririmm) May 31, 2017
ウレタン塗装は手入れがとても楽というメリットがあります。漆と同じく揚げものを入れても染みがつきません。洗うときには中性洗剤が使え、水分を拭き取るか自然乾燥させます。ただし、塗装されている部分と白木の部分がある場合は注意が必要です。
マイナス面は、よい素材を使っていても木の香りがせず、曲げわっぱの特徴である吸湿・殺菌効果が期待できないことです。気軽にお弁当箱として使用し、曲げわっぱの特徴も生かしたい場合は、ごはんの部分は白木でおかず部分に塗装されている種類のものがおすすめです。
ウレタン塗装のお手入れのポイント
大館工芸社の曲げわっぱ3サイズが再入荷いたしました。
秋田杉で作られた手にも目にもあたたかなお弁当箱。
こちらは塗装タイプですので
曲げわっぱ初心者さんにも比較的扱いやすくおすすめです。 pic.twitter.com/evG8Ac45Sh— 良い椅子と日用品と ハッチ家具店 (@torinoiro) September 11, 2019
全体にウレタン塗装が施されているものは、電子レンジや食洗機に入れないといった以外には特に注意することはありません。基本的にプラスチック製品と同じような扱いや手入れでよいので、とても簡単に使用することができます。
一部塗装がされていない部分があるなどの場合には、湿気に弱いなど白木同様の特徴があるので洗い方や乾かし方には注意が必要です。
お弁当箱におすすめの曲げわっぱの形
お弁当箱として販売されている曲げわっぱには、丸型や小判型などさまざまな種類があります。どの種類の形もそれぞれに特徴があります。丸い形の曲げわっぱのお弁当箱は基本的に詰めやすいというメリットがあります。
持ち運びやすさや見た目のかわいさなど、自分にとって重視するポイントから、お気に入りの曲げわっぱを見つけて毎日のお弁当作りやランチを楽しみましょう。
①シンプルで万能な「小判型」
ボラのスダチ酢煮、手羽先、高野豆腐卵とじ、蒟蒻の七味唐辛子・・豆腐とネギのお味噌汁。
雨です(-.-;)y-~~~。#お弁当 #obento #obentoart #obentouLife #曲げわっぱ pic.twitter.com/IlX6rGOVHS
— めみ (@pupumomo17) December 1, 2019
「小判型」の曲げわっぱがおすすめな理由のひとつに、詰めやすいということがあります。また、ごはんとおかずを詰める十分なスペースがあるので、ほとんどの場合は一段で足ります。二段になるとかさばってしまうし、洗うものも増えてしまいます。
もうひとつは、小判型はバッグの中でかさばらないというポイントがあります。楕円形なのでほかの荷物と一緒にバッグに入れてもおさまりがよく、邪魔になりません。曲げわっぱのお弁当の中でも人気の形です。
②インスタ映えするおしゃれな「丸型」
おはようございます。
今日の #お弁当甘辛レモンチキン揚げ、大根葉の菜飯など。#お弁当記録 #地味弁#曲げわっぱ #わっぱ弁当 pic.twitter.com/RMveGo9msr
— さと (@satochan318) December 1, 2019
形がかわいい「丸型」は、どんなおかずを入れてもおしゃれに見えるのが特徴です。楕円形の小判形より若干バッグの中でスペースをとってしまうデメリットがありますが、見た目重視であれば丸型がおすすめです。
③コロンとした形がかわいい「そら豆型」
大館の曲げわっぱ愛用してます◡̈♥︎
そら豆型です。ご飯の水分をわっぱが程良く吸収してくれます。確か以前ラジオで晃教さんも曲げわっぱで食べる白米は美味しいって言ってましたね。
JB大館🎙🎙🎙🎙旅公演初日の成功をお祈りしてます。 pic.twitter.com/gJgnME10A1— milk (@mikimiki_88) October 6, 2018
豆のような形の「そら豆型」も、小判型同様に荷物の中でもかさばりません。そら豆型の曲げわっぱは、キャンプなどでごはんを炊くときに使う「飯盒(はんごう)」に似ていることがから、はんごう型とも呼ばれます。特徴的で、作り方にも職人の技が光る種類の曲げわっぱです。
曲げわっぱでお弁当作りが楽しみに
日本の伝統工芸品の「曲げわっぱ」は、美しい見た目やさまざまな種類の形があり、とても人気です。木の吸湿効果でごはんの水分量がちょうどよい具合に調整され、お弁当に詰めて冷めてしまったごはんも美味しく食べられます。
購入する際に高価なことや、レンジが使えなかったり手入れに注意が必要といった面もありますが、大切に使うことで長く使用できます。お気に入りの素敵な曲げわっぱは、毎日のお弁当作りやランチタイムが楽しみになるアイテムです。制作体験で自分の曲げわっぱを作るのもおすすめです。
おすすめの関連記事
はたやまむつみ
人気の記事
-
「磐梯朝日国立公園」は3県にまたがる公園!その範囲や周辺の温泉は?
-
「フルーティアふくしま」でスイーツ&鉄道旅へ!料金や予約方法は?
-
郡山駅周辺のおすすめランチ17選!便利な安いお店や名物料理の人気店も!
-
山形の大判焼き「あじまん」が絶品!人気商品・販売店舗や営業時間は?
-
福島の桜の名所ランキングTOP25!開花&見頃の時期は?穴場まで紹介!
-
新幹線で足湯を満喫!リゾート列車「とれいゆつばさ」を楽しむ方法とは?
-
東北屈指のパワスポ「出羽三山」を参拝&観光!3つの山と神社を巡る!
-
「山形花笠まつり」は夏の伝統風物詩!その歴史や魅力を徹底解剖!
-
「銀山温泉」へのアクセス方法!東京や大阪など主要都市からのおすすめは?
-
山形のゆるキャラグランプリTOP15!多数のキャラクターの頂点は?
-
山形のご当地名物グルメTOP20!絶品の郷土料理やB級グルメとは?
-
山形のおすすめお土産BEST30!人気のお菓子や雑貨などジャンル別に!
-
ハタハタの卵は虹色?その味や食感は?おすすめ料理のレシピも紹介!
-
秋田のご当地ヒーロー「超神ネイガー」とは?人気グッズや歌を紹介!
-
「日本三大奇祭」とは?それぞれの見所や特徴・その他の奇祭まとめ!
-
秋田のローカル線「由利高原鉄道」で列車旅!魅力や撮影ポイントを紹介!
-
秋田名物・稲庭うどんが東京でも食べられる人気店9選!ランキングで紹介!
-
青森「田舎館村」の田んぼアートを鑑賞!見頃の時期や歴史とは?
-
「岩木山神社」は狛犬が珍しいパワスポ!恋愛運&金運UPの人気神社!
-
青森県民の大好物「イギリストースト」とは?種類や味・由来を解説!
新着一覧
-
西のお伊勢さま!「山口大神宮」参拝のご利益や御朱印&お守りをご紹介!
-
米子「とんきん」は地元で圧倒的人気のカレー専門店!人気メニューは?
-
箱根には魅力的なコテージが満載!大人数やカップルにおすすめコテージ16選!
-
岡山の釣りスポットを大特集!人気スポットや穴場スポット16選
-
【岡山発】皮ごと食べられる「もんげーバナナ」はどこで買える?販売店や通販情報を徹底解説
-
【鳥取県】江府町のおすすめスポット15選!人気の観光地や道の駅、ランチやふるさと納税情報も!
-
【聖地巡礼】「千と千尋の神隠し」の舞台やモデルはどこ?油屋&湯屋に似ている旅館10選を紹介
-
岡山のおすすめ鉄板焼きTOP22!高級店が勢揃い!
-
岡山のおすすめキャンプ場20選!デイキャンプやオートキャンプを厳選!
-
岡山のおすすめ温泉20選!露天風呂や日帰り温泉を厳選!
-
漆黒の城「岡山城」の楽しみ方!見どころや御城印がもらえる場所、周辺の観光スポットを徹底解説
-
倉敷の人気うどん屋TOP22!安くておいしい名店が勢揃い!
-
【岡山】美味しい水はここにあり!「塩釜の冷泉」で喉と心を潤そう!周辺のおすすめスポットも解説!
-
千と千尋は四万温泉がモデル!赤い橋や温泉が楽しめる!
-
海のミルク『寄島の牡蠣』を堪能する旅へ!直売所や通販情報も徹底解説!
-
岡山から鳥取の行き方徹底解説!格安で行ける交通手段は?
-
鬼怒川温泉の廃墟群がヤバい!廃墟になった理由とは?心霊現象が起きる廃墟も!
-
暑い夏には岡山へ!おすすめかき氷店20選!桃やピンスの名物も!
-
【市町村別】岡山のおすすめドライブスポット55選!家族・友達・デート・ひとりでも楽しめる楽しい&絶景スポットを紹介
-
【日本三大産地】岡山の牡蠣は大粒でクリーミー!食べ放題や海鮮BBQ、カキオコの人気店全13選&産地直送の人気通販5選!