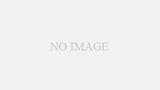「青函トンネル記念館」で壮大な歴史を体験!地下140mの海底を歩く!
青函トンネル記念館ではどんなことが体験できるのでしょうか?せっかくなら世界最長クラスの青函トンネルをもっとダイナミックに感じたいと思いませんか?この記事では青函トンネル記念館でしか味わうことができない魅力と見どころ、その周辺の観光スポットをご紹介します。

目次
青函トンネル記念館とは
龍飛崎にある青函トンネル記念館では、青函トンネルの掘削作業に使われていた坑道(竜飛定点=2013年11月まで青函トンネル・竜飛海底駅だった)に通じている。に入ることができる。 https://t.co/zf7o4ZbMBZ pic.twitter.com/VfoemknoHJ
— パパぱふぅ@pahoo.org (@papa_pahoo) October 4, 2018
日本が世界に誇る世界最長クラスの青函トンネルですが、その青森と北海道をつなぐ海底を走るトンネルの魅力を体験できる施設が「青函トンネル記念館」です。ここでは、青函トンネルの壮大な歴史や海面下140mという海底トンネルのすべてをダイナミックに体験することができます。
この青函トンネルでは実際に使われていた機器の展示や詳しい説明、当時の壮大な工事をたっぷりと体験することができます。この記事では、そんな青函トンネル記念館でしか味わえない魅力や食事やお土産を購入できる道の駅などの周辺の観光スポットも併せてご紹介します。
青森県外ヶ浜町にあるメモリアル施設
青函トンネル記念館というところにも行きました🎉(龍飛岬の手前にあるよ)
斜坑線に乗って地下にもぐり、青函トンネルを掘る時に使った作業トンネルを歩いて当時の様子を体験できるものなんですが、これがとても興味深かったのです。 pic.twitter.com/DPWCv7jiJV— あまの (@ou_ewe) October 17, 2019
北海道と青森を隔てる津軽海峡を貫通した青函トンネルは、青森県側が入口、北海道側が出口と定義されています。その入口側である青森県の外ヶ浜町に当時の貴重な資料、実際に使われた機械などを伝えるメモリアル施設として青函トンネル記念館が建てられました。
青函トンネル記念館の魅力
「竜泊ライン」を更に北上し竜飛岬が近づいて来ると「青函トンネル記念館」があります。ここで是非お勧めしたいのが海面下140mの別世界にある駅「体験坑道駅」そして実際の青函トンネルまでは行けませんがそのすぐ近くまで近づく事が出来るんです。#青森 #Aomori #青函トンネル記念館 pic.twitter.com/0kdOStCbYn
— 三九 酒縁 【公式】 (@39aomori) September 19, 2017
青函トンネル記念館の最大の魅力は、なんといってもここでしか体験できない青函トンネルに降りて歩くという「坑道体験」です。海底140mまでケーブルカーを使って自分の足で行くことができます。
そんな青函トンネルの魅力をよりダイナミックに感じるために、この青函記念館でしか味わえない見どころを行く前にしっかりと押さえておきましょう。この魅力を体感した後は、併設の道の駅でお土産を購入したり特産の海の幸を使った食事を楽しむこともできますよ。
青函トンネルとは
この前青函トンネルから出てきた新幹線はやぶさ激写したわ🚄 pic.twitter.com/Q7dZpE3nni
— 一輝 (@turikazu9759) November 21, 2019
青函トンネルとは、全長53.85km最大で海底140mを走る、本州と北海道を貫く海底トンネルです。寝台特急北斗星の運用が終了し、2016年には新幹線が開通、2019年3月からはその時速が160km/hまでに引き上げられ再注目を浴びています。
この海底トンネルが掘られた地層は、氷河期に本州と北海道を繋いでいた山脈にあたり、かつてはナウマン象が行き来していたとも言われています。そんな古い海底深くにトンネルを掘る大工事は非常に困難であったと今でも知ることができます。
世界最長の海底トンネル
青函トンネルの坑道へ
青森と函館を繋げようとした男たちロマンを感じる pic.twitter.com/WixkkRXAjF— BLACKPEARL (@blackpearl4110) July 29, 2016
実はこの青函トンネル、1988年に開通して以来2019年の現在でも、海底トンネルとして世界一の長さと深さを誇る「世界最長の海底トンネル」です。つい最近の2016年に開通したスイスのゴッタルド・トンネルが誕生するまでは、「世界一長い鉄道トンネル」としてもその名を世界に響かせていました。
そのためこの難工事は当時の最先端の技術が集まり、世界中から注目を浴びていたとも言われます。その技術のひとつひとつを青函トンネル記念館では、実際の機器を見ながら詳しく知ることができます。
構想から貫通まで42年
青函トンネル貫通石 pic.twitter.com/EDqJa4bYwO
— 織春 紺太郎 (@monyo8500) October 6, 2018
その着工期間はとても長く、着工開始から1988年(昭和63年)の開通まで、実に42年もの歳月をかけて誕生しました。
この海底を貫く歴史的大工事では、34人もの殉職者を出した前例のない難工事だったことも有名です。大きな水圧がかかる中での工事のため、異常出水などの様々な困難を乗り越えて完成までたどり着きました。現在、青函トンネル記念館にはその慰霊碑が建てられています。
青函トンネルの歴史を学べる記念館
青函トンネル記念館では体験坑道に参加
使用車両はケーブルカーでとんでもない勾配の道を大きな音をたてながら進むため、乗っているだけなのにヒヤヒヤした
体験坑道だけでなく記念館の展示も、いかにして青函トンネルが作られたかということを細かく知れた感想は『青函トンネル凄い』の一言に尽きる pic.twitter.com/2lSb8WJezM
— Nmiura d (@Nmoto1731) July 28, 2019
教科書でもその歴史には深く触れられていない青函トンネル、この青函トンネル記念館では世界に誇る大工事の全貌が立体モデルや映像で再現されています。お子さまから年配の方までわかりやすくその歴史を学ぶことができます。
地下140mの海底を歩ける
青函トンネル坑道体験
FalloutのVaultみたい pic.twitter.com/OFtzawlA2A— あおい (@aoisupersix) September 16, 2019
この青函トンネル記念館では、海底140mの坑道を実際に自分の足で歩くことができるのも嬉しいポイントです。実際に使われていた日本で一番深い場所に、自分の足で立って歩き進むのは、電車で通り過ぎるだけでは絶対に味わえない圧倒的な空気に飲まれます。
道の駅「みんやま」に併設
3駅目 道の駅 みんまや 竜飛岬
スタンプゲット👍 pic.twitter.com/XRST5Lh0AT— とし@亀なライダー (@104kamena_Rider) November 3, 2019
青函トンネル記念館には、道の駅「みんやま」が併設されています。こちらは津軽海峡最北端の道の駅であり、道の駅スタンプラリーやお土産に国道339号線のステッカーを購入できる場所としても一部の間で知られています。
青函トンネル記念館に併設されているため、駐車場が同じでその料金は無料です。トイレ休憩ができるだけでなく、食事処やお土産ショップもあるのでぜひチェックしてみてください。
食事処やお土産ショップも
記念館のレストラン海峡味処紫陽花でお昼。
美味しかった。
予断ながら、店名のあじさいに警戒感を示す関東組(笑 pic.twitter.com/Kke7vmT2kU— 駅長 山本留吉 (@Y_Tomekiti) November 6, 2017
こちらには食事ができる海鮮味処「紫陽花」があり、特産品の海の幸を使った大漁刺身定食や海鮮丼、磯うにラーメンや海鮮五目ラーメンなどの食事が1000~2000円程の料金で味わうことができます。海の幸を使用するので、季節で食事内容が変わることもあります。
お土産販売コーナーもあり、この地方の特産品「若生昆布」「みんやま昆布」に加えオリジナルグッズをお土産として購入することもできます。特にお土産として人気があるのは、トンネル内の湧水をそのまま使って24時間冷水抽出した「水出しコーヒー龍飛」です。
北海道にも青函トンネル記念館
今日は福島町🚕
まずは青函トンネル記念館🚝
昭和36年から建設が始まって昭和63年に開通した青函トンネル。
その歴史がわかる記念館です🚝
見応えありましたよ!#道南ハイヤー #函館観光 #函館 #福島町 #青函トンネル記念館 pic.twitter.com/TQPL5VUC5t— 道南ハイヤー株式会社 (@dounan_taxi) August 23, 2019
実は北海道側にも青函トンネル記念館があり、北海道側からの拠点となった福島町の跡地に位置しています。こちらでも巨大なトンネルボーリングマシンが見られるなど、当時の工事風景やトンネルの着工に至った経緯などの歴史を学べる観光スポットとなっています。
北海道側の青函トンネル記念館でしか買えない限定のお土産やオリジナルグッズもあるので北海道側に立ち寄る場合は見逃せません。どちらも表記が「青函トンネル記念館」なので、くれぐれも青森側と北海道側を間違えないように注意しましょう。
青函トンネル記念館の見どころ
青函トンネル記念館の記念メダル。 ケーブルカーで地下深くまで潜って青函トンネルを実際に歩く体験をしました。 pic.twitter.com/i8kUcDo7u6
— 九十九@2日目西れ42a (@tukumo99) September 26, 2019
青函トンネル記念館ではたくさんの見どころが用意されています。展示にギャラリーや映像などでしっかりと歴史とその工事の凄さを体感した後に、海底140mの坑道体験に進んだ時の感動はひとしおです。
坑道体験のケーブルカーの時間や、帰りの時間の追われて見逃しのないように、前もって青函トンネル記念館のそれぞれのゾーンについてチェックしておきましょう。せっかく訪れるからには体験証明書と記念メダルを自分へのお土産にするのもおすすめです。
見どころ①展示ホール
青函トンネル記念館、プロジェクトX的な感じの展示が多くて大満足でした。 pic.twitter.com/26V0q1MYOj
— やるせ (@yaruse_34) April 20, 2019
実はこの青函トンネルの工事では、多くの新しい技術がここで生み出されました。「吹付コンクリート技術」「先進ボーリング技術」「注入コンクリート技術」は三大技術とされ、その後のトンネル工事の技術発達の基盤となりました。
そんな最先端の技術の結晶によって進められたこの工事は、世界中が注目していたとも記録が残っています。そんな技術の歩みをこの青函トンネル記念館では詳しく知ることができます。
見どころ②ギャラリー(工事の歴史)
青函トンネル記念館。青函トンネル工事の際に使われた道具、トロッコ、資料、トンネルの模型などが置かれている。(2013年11月 青森県竜飛崎) pic.twitter.com/JyQdxSqTSG
— 旅行写真bot (@pic_travel) November 13, 2015
青函トンネル記念館の2階に上がると工事の歴史のその経緯を詳しく紹介しています。立体模型や数々の資料から、当時の歴史を知ることができます。
ここでは実際に使われた機器なども展示されており、いかに難しい工事であったか感慨深い展示となっています。じっくりと深く見て回ると時間が足りなくなる程の歴史がこの青函トンネル記念館に詰まっています。
見どころ③トンネルシアター
青函トンネル記念館に行ってきた!
50km以上の距離のトンネルってすげぇなぁと改めて思うねぇ(・・;)
シアタールームでは当時の映像を使ったムービーも見れます!
新幹線開業がより感慨深く感じられるので興味ある方はぜひ!! pic.twitter.com/gKXtRsIdmU— 得猫@日本一周してたそうな… (@gutokuneko) August 6, 2017
同じく青函トンネル記念館の2階には、トンネルシアターというシアタールームがあります。長い年月と暑い情熱をかけて海の底を掘り進めた、この大工事に関わった人々の舞台裏と壮大なドラマを22分間の映像で楽しむことができます。
ここで見ることができる映像は実際の記録映像を用いて作られているため、調査から貫通の瞬間までの長い歴史を、まるで自分も当事者になったように見入ってしまいます。
見どころ④地下140mの体験坑道
青函トンネル記念館 体験坑道
#良い通路の日 pic.twitter.com/GZkV7LmQtp
— 鈴木✴︎しげない工房✴︎ (@dankosuzu) November 25, 2017
ここが青函トンネル記念館の最大の魅力、いよいよ海面下140mの別世界へと足を踏み入れる「体験坑道」です。実際に工事作業に使われた地下坑道へケーブルカーを使って一気に向かいます。まるで別世界へ向かうような臨場感たっぷり迫力満点の世界へ出発です。
坑道体験は青函トンネル記念館の入場料とは別で料金が必要となります。入場時の窓口でセット割引があるので、はじめにケーブルカーの出発時間と併せてチェックしておきましょう。
青函トンネル竜飛斜坑線 もぐら号
青函トンネル記念館から体験坑道まで
青函トンネル記念館→体験坑道:青函トンネル竜飛斜坑線#かえざくら乗車録 #かえざくら旅行 pic.twitter.com/0y5vpMMdfe
— かえざくら@11/31~12/1:札幌、小樽 (@kae_sakura) October 7, 2018
この一番人気の観光スポットである「坑道体験」その海の底へ向かうために、青函トンネル竜飛斜坑線モグラ号に乗り込みます。この日本一短い私鉄は、青函トンネルの地下坑道までの斜度14度の斜坑をわずか7分で一気に駆け下ります。
降りていくときの海底深くの別世界へ入るドキドキ感はこの青函トンネル記念館でしか味わえません。また、ここから海底140mに降りると戻るまでにたっぷり約45分の時間を要します。そのため、食事や帰りの時間を確認しておくことをおすすめします。
見どころ⑤坑道内の特別展示エリア
体験坑道には、青函トンネルに関わる様々な展示がある。また、建設の苦労を描いた上映フィルムは泣かせてくれる。 pic.twitter.com/R3yctzV7cy
— まっきぃ@11/29(金)新中野弁天歌ものセクション (@makki629) September 22, 2013
ひんやりと寒い海底140mの地下坑道には当時の現場と実際に掘削に使用されていた機械や機器が展示されています。坑道内では、青函トンネル記念館の案内係の方が説明をしながら約20分かけてじっくりと案内をしてくれます。
その案内のトークに聞き入りながらこの冷たい海底の空気の中で見る展示は、その過酷さから多くの人々の苦労があった現場であったと、改めてひしひしと感じる歴史の重みのある空間となっています。
青函トンネル記念館周辺の観光スポット
【龍飛崎】
名前の由来になったように、龍が飛び立ったかのような強風が吹いてます。そして、昨日までいた北海道がぼんやりと見えます!
付近には津軽海峡冬景色の歌謡碑や階段国道、義経伝説のある帯島など見所沢山です😁 pic.twitter.com/sQIzxc6SVG— RYO (@ryoimai7) August 1, 2018
じっくりと青函トンネル記念館の世界を堪能した後は、せっかくなら周辺の観光スポットも訪れてみてはいかがでしょうか。高台からは本州と北海道を隔てる津軽海峡やその海峡を行き交う船舶を見渡すこともできます。
天気のいい日は北海道の松前半島が見える観光スポットとして、その景色の良さが人気です。このあたりは渡り鳥の飛行ルートとしても知られ、鳥類研究会の方が観察していることもあるそうです。
スポット①龍飛埼灯台
龍飛埼灯台なう!風がつよいぜ! pic.twitter.com/PKMAKg4BRK
— ペケ太★休日ライダー (@maruchan827) August 13, 2019
竜飛埼(たっぴさき)はアイヌ語の「タム・パ(突き出た地)」が由来とされ、「龍が飛ぶ」と書いて「たっぴ」と当て字されたとも言われます。その名の通り龍が飛ぶほど風が強く、雪すらも風に飛んで積雪も少ない程です。
そんな竜飛埼の高台には灯台が立ち、日本の灯台50選にも選ばれています。周辺は津軽国定公園にも指定されており、晴れた日の眺めは絶景です。ドライブで特産品を購入して「この灯台周辺で食事休憩」というには風が強すぎたりするので気を付けてくださいね。
龍飛埼灯台の基本情報
| 【名称】 | 竜飛埼灯台 |
| 【住所】 | 〒030‐1711 青森県東津軽群外ヶ浜町字三厩龍浜 |
| 【アクセス】 | JR三厩駅前より外ヶ浜町循環バスの乗車 (所要時間役30分)終点竜飛埼灯台下車。 |
| 【料金】 | 見学自由 |
| 【参考HP】 | https://www.aptinet.jp/Detail_display_00000066.html |
| 【備考】 | 竜飛埼観光案内所 0174-31-8025 |
スポット②階段国道
酷道の中でも最強クラスと噂の階段国道にきました! pic.twitter.com/8HUqKuTy0o
— こたつ (@kotatu_travel) August 26, 2017
階段国道は国道339号のルートの中にあり、日本唯一の車が通ることができない国道です。竜飛埼灯台から竜飛後光付近までの急な崖を結ぶ362段の階段が階段国道と呼ばれています。かつては周辺小中学校の通学路として利用されていました。
階段が国道となった経緯としては諸説あり、役人が地図上だけ見て国道にした説や、青函トンネルの工事の際の道路整備として階段と知りながら国道とされたという説など。また通学路だったころは坂道であったというのが有力なようです。
階段国道の基本情報
| 【名称】 | 階段国道339号 |
| 【住所】 | 東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜 |
| 【アクセス】 | 竜飛漁港バス停から階段国道を通って灯台まで徒歩約15分 |
| 【料金】 | 見学自由 |
| 【参考HP】 | https://www.aptinet.jp/Detail_display_00000413.html |
| 【備考】 | 冬季閉鎖期間あり 問い合わせ先 外ヶ浜産業観光課 |
スポット③津軽海峡冬景色歌謡碑
龍飛の歌謡碑
まさに津軽海峡冬景色
大音量の津軽海峡冬景色でした#津軽海峡冬景色 pic.twitter.com/DToxODHlOj— ドランクアングラー (@drunkangler77) January 30, 2017
津軽海峡を見下ろす高台には、石川さゆりさんの名曲「津軽海峡・冬景色」の歌謡碑があります。歌謡碑のボタンを押すと、名曲の世界観を見下ろしながら「ごらんあれが竜飛岬北のはずれと…」と津軽海峡冬景色の2番が流れるようになっています。
津軽海峡の大波をイメージして作られたこの石碑からは、風が強いこの高台でも負けないほどの大音量で流れることも話題になりました。海を眺めながらこの世界観に浸ってみてはいかがでしょう。
津軽海峡冬景色歌謡碑の基本情報
| 【名称】 | 津軽海峡冬景色歌謡碑 |
| 【住所】 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜 |
| 【アクセス】 | JR三厩駅前より外ヶ浜町循環バスの乗車 (所要時間役30分)終点竜飛埼灯台下車すぐ |
| 【料金】 | 見学自由 |
| 【参考HP】 | https://www.aptinet.jp/Detail_display_00003481.html |
| 【備考】 | 駐車場あり(50台) |
青函トンネル記念館の詳細情報
青函トンネル記念館へ
青函トンネルの、地質調査開始から
開通までの歴史が載っていて、
入館料(400円)+1000円で、
実際の作業坑も入れることが出来ます右下は400メートル先に新幹線が通ってるらしいです。 pic.twitter.com/BPJVLny5LX
— ルカ自転車日本一周中 (@rukafromkyoto) August 21, 2019
青函トンネル記念館は、雪が深くなる期間は冬季休業となっています。天候によっては変更となることも想定されており、毎年の公式HPで営業日が記載されているのでしっかりチェックしておきましょう。
ここでは青函トンネル記念館の最低限チェックしておきたい営業時間やアクセス方法、駐車場情報などご紹介します。入場券と坑道体験をセット割引でお得に購入する方法もありますよ。
青函トンネル記念館の営業期間&時間
今日の道中、postする暇がなかったとことか…
竜飛崎は青函トンネル記念館。ここはいつ行っても強風が吹き荒れてるイメージしかない…今日もエグいくらいの突風。
記念館前にある碑が地味にカッコよくて好き pic.twitter.com/vvGXDHmBsn— さーーーたり (@sawatara) May 20, 2017
厳しい環境のため冬季休業を設けている青函トンネル記念館の開館期間は、およそ4月20日頃~11月5日頃までです。この開館している期間中は定休日は無く無休営業です。正確な開館期間は、天候により変更になることもあるため公式HPで確認をしておくことが必要です。
開館期間中の青函トンネル記念館の営業時間は午前8時40分~午後5時です。坑道体験で海底へ向かう場合は、約45分ほどの時間を要するため前もってバスの時間などをチェックしておきましょう。海底に潜る前に食事の時間を考えておくことも忘れずに。
青函トンネル記念館の入館料金
体験坑道乗車券買ったけど、順番逆にすりゃよかったなあ、、1040の便、バスの時間ギリギリか場合によって間に合わない…
戻り11:24
バス11:22ころ(目安、乗降フリー)#道路人秋の北方旅17 pic.twitter.com/oiT56k4BaQ— 道路旅人 (@traveller_3104k) October 8, 2017
青函トンネル記念館の入館料は、大人400円、小人200円となっています。これは記念館自体の入館料なので、「体験坑道」は別で大人1,000円、小人500円の体験坑道乗車券が必要です。障碍者手帳などをお持ちの場合は、窓口での手帳の提示で入館料が半額割引となります。
団体の場合は割引があり、普通団体20名以上で1割引、50名以上で2割引、学生団体20名以上で2割引、50名以上で3割引となります。団体で利用する場合は事前に記念館への連絡が必要となります。
体験坑道乗車券とセットで割引
本日は 竜飛海底駅見学コース 参加者は35人だそうです。案内人さんのトークが凄く面白いです! 体験証明書と坑道乗車券です。 pic.twitter.com/l7W5medwPV
— 飛鳥 (@akira1837) September 1, 2013
青函トンネル記念館の入場券と体験坑道乗車券を合わせて購入すると、特別セット割引として大人1,300円、小人650円で購入することができます。このセット割引は記念館の窓口で購入が可能です。
後から体験坑道の乗車券を購入もできますが、はじめにセット割引で購入しておく方がお得です。体験坑道を見学した後はお土産に「体験証明書」を貰えるので、ぜひ観光の思い出として必ず受け取っておきましょう。
青函トンネル記念館へのアクセス
青函トンネル記念館へのアクセスは、公共交通機関・車のどちらでも行くことができます。それぞれの場合のアクセス方法と駐車場などの情報をご紹介します。ぜひ、青函トンネル記念館にアクセスして青函トンネルの魅力を思いっきり楽しみましょう。
公共交通機関を利用する場合
というわけで青函トンネル記念館バス停から1分遅発(乗車人数多く時間かかった結果)の外ヶ浜町三厩地区循環バス(循環しません)三厩駅前行きに乗りました。100円なのはホントありがたい! pic.twitter.com/as2cKE4bIp
— よねざわいずみ (@yonezawaizumi) June 29, 2019
青函トンネル記念館まで公共交通機関を使う場合は、JRの三厩駅からバスへの乗り換えが必要となります。JR三厩駅から外ヶ浜町巡回バス(三厩地区巡回バス)龍飛行きへ乗車、青函トンネル記念館で下車。バスの所要時間は約27分です。
公共交通機関を利用する際は、青函トンネル記念館で展示コーナーを回る時間と坑道探検に要する時間、食事をする場所や時間を考慮し帰りのバスの時刻表を控えておきましょう。
車・レンタカーを利用する場合
新幹線を奥津軽いまべつで降り、レンタカーで青函トンネル記念館へ
このケーブルカーも乗りつぶし対象なので… pic.twitter.com/toC10cSqBC— 23区のどれか (@tandenmax) May 11, 2019
車・レンタカーで青函トンネル記念館へ向かう場合は、東北自動車道青森ICから約80㎞となっています。青森ICから国道7号で津軽方面へ進み、新城大橋を渡り国道280号へ左折。津軽海峡、龍飛埼で案内板に従い現地へ向かいます。
観光でレンタカーを使用する場合、雪道の運転に慣れていないと寒い時期の悪天候の際は車で向かうことが難しくなるため、季節と天候はしっかり確認しておくことをおすすめします。
駐車場情報
青函トンネル記念館にて。
入口の手前には、天皇陛下皇后陛下の御訪問記念碑があり、青函トンネルを出てくるED79 17牽引の快速「海峡」が刻まれていた。
その隣には海底下100mから持ってきた石が展示されていた。
駐車場の裏の山には「青函トンネル本州方基地龍飛」の看板があった。 pic.twitter.com/siO9N4XqBQ
— ばふぁろうず@11/24京セラドーム大阪 (@itemae_spirits) October 25, 2018
青函トンネル記念館には駐車場が用意されており、駐車料金は無料です。普通車178台・大型車10台・身障者駐車場2台です。マイクロバスなどを利用する場合は駐車場が異なり、事前連絡が必要となります。
青函トンネル記念館の駐車場そばには、日本海を見下ろす広場に屋外展示があるのも見どころのひとつです。海底から持ち出した石や、水平人車・斜坑人車・アジテーターカーなど実際に使われていた設備が説明付きで展示されていますぜひこちらもチェックしてみてください。
青函トンネル記念館の基本情報
青函トンネル記念館で青函トンネルについて学んでからそれを通る学生の鑑 pic.twitter.com/MYga5RlX8f
— はまーん (@hamaaaaan_StMe) August 28, 2018
| 【名称】 | 青函トンネル記念館 |
| 【住所】 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜99 |
| 【TEL】 | TEL 0174-38-2301 |
| 【料金】 |
入館料 大人400円 小人200円 団体利用の場合、 |
| 【公式HP】 | http://seikan-tunnel-museum.jp/index.html |
| 【備考】 | 冬季休業あり、開業時期は定休日なし 詳細は公式HPをチェックください。 |
青函トンネル記念館で歴史を体感しよう
竜飛の青函トンネル記念館は17年ぶりの再訪。屋外で展示されている水平人車はどうやら腐食と積雪で天井が落ちてしまったようだ。#保存車の記録 pic.twitter.com/oJH39zA64H
— 出てこいシャザーン (@kutunoura6) June 28, 2018
青函トンネル記念館とその周辺の観光地についてご紹介しました。この海底140mを通って本州と北海道をつなぐ青函トンネルの壮大なドラマと歴史、知られざる魅力を探りにぜひじっくりとこの記念館を訪れてみてください。
せっかく青森県まで来たら、他にもぜひ訪れたい観光スポットや特産の海の幸を使った美味しい食事、お土産を探しに行ったりとおすすめスポットがまだまだたくさんあります。そちらもぜひチェックしてみてください。
おすすめの関連記事
oshita-m
人気の記事
-
「磐梯朝日国立公園」は3県にまたがる公園!その範囲や周辺の温泉は?
-
「フルーティアふくしま」でスイーツ&鉄道旅へ!料金や予約方法は?
-
郡山駅周辺のおすすめランチ17選!便利な安いお店や名物料理の人気店も!
-
山形の大判焼き「あじまん」が絶品!人気商品・販売店舗や営業時間は?
-
福島の桜の名所ランキングTOP25!開花&見頃の時期は?穴場まで紹介!
-
新幹線で足湯を満喫!リゾート列車「とれいゆつばさ」を楽しむ方法とは?
-
東北屈指のパワスポ「出羽三山」を参拝&観光!3つの山と神社を巡る!
-
「山形花笠まつり」は夏の伝統風物詩!その歴史や魅力を徹底解剖!
-
「銀山温泉」へのアクセス方法!東京や大阪など主要都市からのおすすめは?
-
山形のゆるキャラグランプリTOP15!多数のキャラクターの頂点は?
-
山形のご当地名物グルメTOP20!絶品の郷土料理やB級グルメとは?
-
山形のおすすめお土産BEST30!人気のお菓子や雑貨などジャンル別に!
-
ハタハタの卵は虹色?その味や食感は?おすすめ料理のレシピも紹介!
-
秋田のご当地ヒーロー「超神ネイガー」とは?人気グッズや歌を紹介!
-
「日本三大奇祭」とは?それぞれの見所や特徴・その他の奇祭まとめ!
-
秋田のローカル線「由利高原鉄道」で列車旅!魅力や撮影ポイントを紹介!
-
秋田名物・稲庭うどんが東京でも食べられる人気店9選!ランキングで紹介!
-
青森「田舎館村」の田んぼアートを鑑賞!見頃の時期や歴史とは?
-
「岩木山神社」は狛犬が珍しいパワスポ!恋愛運&金運UPの人気神社!
-
青森県民の大好物「イギリストースト」とは?種類や味・由来を解説!
新着一覧
-
西のお伊勢さま!「山口大神宮」参拝のご利益や御朱印&お守りをご紹介!
-
米子「とんきん」は地元で圧倒的人気のカレー専門店!人気メニューは?
-
箱根には魅力的なコテージが満載!大人数やカップルにおすすめコテージ16選!
-
岡山の釣りスポットを大特集!人気スポットや穴場スポット16選
-
【岡山発】皮ごと食べられる「もんげーバナナ」はどこで買える?販売店や通販情報を徹底解説
-
【鳥取県】江府町のおすすめスポット15選!人気の観光地や道の駅、ランチやふるさと納税情報も!
-
【聖地巡礼】「千と千尋の神隠し」の舞台やモデルはどこ?油屋&湯屋に似ている旅館10選を紹介
-
岡山のおすすめ鉄板焼きTOP22!高級店が勢揃い!
-
岡山のおすすめキャンプ場20選!デイキャンプやオートキャンプを厳選!
-
岡山のおすすめ温泉20選!露天風呂や日帰り温泉を厳選!
-
漆黒の城「岡山城」の楽しみ方!見どころや御城印がもらえる場所、周辺の観光スポットを徹底解説
-
倉敷の人気うどん屋TOP22!安くておいしい名店が勢揃い!
-
【岡山】美味しい水はここにあり!「塩釜の冷泉」で喉と心を潤そう!周辺のおすすめスポットも解説!
-
千と千尋は四万温泉がモデル!赤い橋や温泉が楽しめる!
-
海のミルク『寄島の牡蠣』を堪能する旅へ!直売所や通販情報も徹底解説!
-
岡山から鳥取の行き方徹底解説!格安で行ける交通手段は?
-
鬼怒川温泉の廃墟群がヤバい!廃墟になった理由とは?心霊現象が起きる廃墟も!
-
暑い夏には岡山へ!おすすめかき氷店20選!桃やピンスの名物も!
-
【市町村別】岡山のおすすめドライブスポット55選!家族・友達・デート・ひとりでも楽しめる楽しい&絶景スポットを紹介
-
【日本三大産地】岡山の牡蠣は大粒でクリーミー!食べ放題や海鮮BBQ、カキオコの人気店全13選&産地直送の人気通販5選!